ビジネスわかったランド (経営・社長)
事業承継と相続対策
遺言書の作成の仕方は
遺言がないばかりに、遺産分割協議でもめにもめて何年にもわたってやっと協議が調ったという例は枚挙にいとまがない。相続でのトラブルになると、たとえ決着がついたとしても、お互いに心の傷が残り、もはや以前の親族関係の修復はむずかしい。それを避ける方法として、遺言書を作成することが大切であるが、遺留分なども念頭に置いて、公正証書遺言にしておくのがベターである。
ぜひとも遺言しておきたいケース
被相続人の意思を相続にきちんと反映させたい場合は、遺言を残すことが必要である。その例としては、次のようなケースがあげられる。
1.法定相続人でない人に遺産を譲りたい場合
a.夫婦が内縁関係であった場合
いわゆる内縁関係の場合、いくら長い間夫婦同然のように一緒に暮らしてきても、内縁の妻(あるいは夫)には相続権がない。したがって、財産を譲る場合には遺言が必要。
b.息子の嫁に遺産を譲りたい場合
親に先立って死亡した息子の嫁が、その後も引き続き一緒に暮らして面倒をみてくれているような場合、死亡した息子の嫁は、義理の父の遺産については全然相続権はない。血はつながらずとも面倒をみてくれた嫁へ愛のプレゼントといったケースでは遺言として残しておく必要がある。
c.孫や生前格別世話になった人に遺産を譲りたい場合
孫や、生前に格別にお世話になった人など、相続人以外の特定の人に財産を残したい場合等、遺言でその内容をはっきりさせておく。
2.法定相続分と異なる分け方が好ましい場合
a.事業経営者の場合
たとえば、長男を自分の後継者として事業経営に当たらせたいと考える場合には、他の相続人へ配慮しつつ、しっかりとその旨を意思表示しておく必要がある。それと同時に、事業のための財産の継承問題についても、相続人間で的確に分配を定めておき、経営が安定するよう配慮しておくことが肝要である。すなわち、事業承継と後継者の選定、没後の同族会社の健全経営等、あらゆる面で総合的に考えた遺言が必要である。
b.障害のある子どもや未成年の子どもがいる場合
たとえば、身体に障害のある子どもに、他の子どもよりも多めに遺産を残しておきたいとか、相続人が未成年であるなど、親としては残された子どもの将来のことが非常に気になる場合は遺言をしておいたほうがよい。
3.遺産の分割協議がむずかしいと思われる場合
a.再婚して後妻と先妻の子供がいる場合
先妻の子どもと新しい妻との間は感情的に対立しがち。先妻の子どもにすれば、父が再婚しなければ全財産を相続できるはずであったのに、ということになる。一方、新しい妻の方は2分の1の相続分があるはずだと主張しがちである。夫としては、後妻も自分の妻であり、老後を共に過ごした人であるから、後妻の老後の生活の安定も図りたい。また、後妻には先妻の子どもたちと仲良くやっていってもらいたい。そのことを遺言の中で触れておく。
b.一部の相続人に生前贈与をしている場合
一部の相続人に生前贈与している場合、残りの財産の帰属について口頭で自分の考えを話していることが多い。しかし、口頭の遺言は認められていないのでかえって混乱が生じる。はっきりと遺言書で決めておくべきである。
c.遺産が不動産など分けにくい物である場合
現金や預金は分けるのが容易である。しかし、不動産の場合は分けにくく、相続人間で争いが生じる。それを避けるために、遺言書で分け方を決めておくとよい。
d.相続人の中に協調性のない人がいる場合
相続人の全員が協調性のある人の場合は、分割もスムーズにいくが、残念なことにそうではないケースもある。そのような場合に備え遺言書を書いておくと相続人は助かる。
e.夫婦間に子供がいない場合
夫婦に子供がいない場合、長年夫婦で協力して築き上げてきた財産なら、先立つ者としては全財産を配偶者に相続させたいと思うこともある。民法では、子や孫がいない場合には配偶者と親が、また親もいない場合には配偶者と兄弟姉妹が相続人と定められている。したがって、遺産の多くを配偶者に与えたいときは、どうしても遺言ではっきりさせておくべきである。
4.法定相続人がいない場合
遺産を引き継ぐ相続人がいない場合には、一定の手続きを経て国に財産が帰属する。生前世話になった人や親しい友人に財産を譲りたい、あるいは社会福祉団体などに寄附したいと考えているのであるならば、そのように遺言しておくことが必要である。
遺言書の種類とその特徴
1.自筆証書遺言
自筆証書遺言は、全文自分で書き(手書き)、日付、氏名押印が必要である。訂正する場合も細かな規定があるので、書き直したほうがよい。
これは、遺言書を1人で作成できるので簡単である。ただし、記載内容が不明確で、遺言者の意思がうまく表現されていなかったり、形式が遺言書と認められない例もあるから、弁護士に相談して書くことをお勧めする。
自筆証書遺言は、遺言者が死亡した場合、家庭裁判所で検認手続きをする必要がある。
2.公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人に作成してもらうもので、証人2人が必要である。
通常は公証人役場に出かけて作成するが、病気等で行けない場合は出張もしてもらえる。
この方式の場合、死後に遺言書の有効性が争いになることはほとんどない。
3.死亡危急者の場合の特別方式
死亡の危急に迫った者が遺言しようとする場合は、特別の方式がある。
これらをまとめると次の図表のようになる。
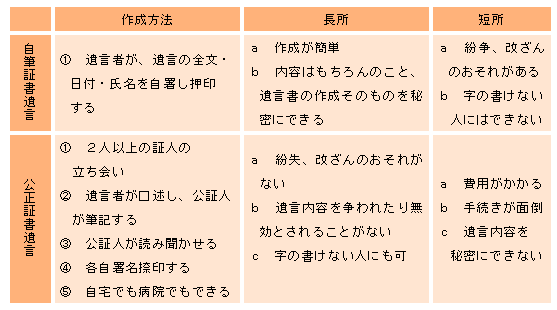
遺言書の例は、次のようになる。
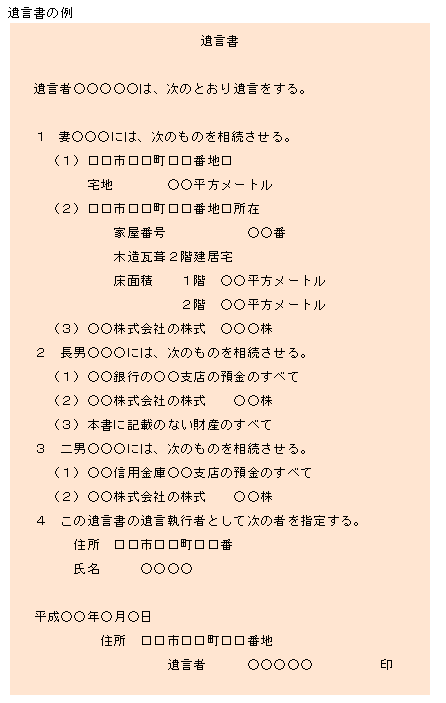
遺留分があること
被相続人の遺言により相続において財産を何ももらえなかったり、わずかしか財産をもらえない相続人が出るなど不公平が生じることがある。そこで、相続財産のうち一定割合額だけは相続人に保障しようとするのが遺留分の制度である。
1.遺留分権利者……配偶者、子、父母(兄弟姉妹には遺留分はない)
2.遺留分の割合……財産全体の2分の1(父母のみが相続人のときは3分の1)
たとえば、夫が死亡し、妻と長男、長女が相続人で、夫が長男に全財産2億円を与えると遺言していたケースでは、次のようになる。
・妻の遺留分=2億円×2分の1(遺留分率)×2分の1(法定相続分)=5,000万円
・長女の遺留分=2億円×2分の1(遺留分率)×4分の1(法定相続分)=2,500万円
妻は5,000万円、長女は2,500万円の遺留分を持ち、その分だけ財産を取り戻すことができる。この権利を遺留分減殺請求権という。
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が遺言分を侵害されたことを(遺言書の内容で)知ったときから、1年間行使しないときは時効により消滅する。
遺言書の保全
公正証書による遺言書は、公証役場に保管されているので、紛失のおそれはない。しかし、自筆証書や特別方式による遺言書は発見されにくい場所に隠しておくなどにより、遺言者の死後も発見されないままになってしまうことがある。
そこで、信頼のおける友人や税理士、弁護士に預けたり、銀行の貸金庫に預けたりして保管しておくのが望ましい。
遺言書が出てきたとき
公正証書による遺言書は、そのまま遺言書の内容を執行できる。
自筆証書や特別方式による遺言書は、公開されていないので、被相続人のものかどうかを確認(検認の請求)することが必要である。この検認(確認)は家庭裁判所で相続人立会のもとに開封して行なう。
著者
中山 昭男(相続コンサルタント)
2006年9月末現在の法令等に基づいています。
ぜひとも遺言しておきたいケース
被相続人の意思を相続にきちんと反映させたい場合は、遺言を残すことが必要である。その例としては、次のようなケースがあげられる。
1.法定相続人でない人に遺産を譲りたい場合
a.夫婦が内縁関係であった場合
いわゆる内縁関係の場合、いくら長い間夫婦同然のように一緒に暮らしてきても、内縁の妻(あるいは夫)には相続権がない。したがって、財産を譲る場合には遺言が必要。
b.息子の嫁に遺産を譲りたい場合
親に先立って死亡した息子の嫁が、その後も引き続き一緒に暮らして面倒をみてくれているような場合、死亡した息子の嫁は、義理の父の遺産については全然相続権はない。血はつながらずとも面倒をみてくれた嫁へ愛のプレゼントといったケースでは遺言として残しておく必要がある。
c.孫や生前格別世話になった人に遺産を譲りたい場合
孫や、生前に格別にお世話になった人など、相続人以外の特定の人に財産を残したい場合等、遺言でその内容をはっきりさせておく。
2.法定相続分と異なる分け方が好ましい場合
a.事業経営者の場合
たとえば、長男を自分の後継者として事業経営に当たらせたいと考える場合には、他の相続人へ配慮しつつ、しっかりとその旨を意思表示しておく必要がある。それと同時に、事業のための財産の継承問題についても、相続人間で的確に分配を定めておき、経営が安定するよう配慮しておくことが肝要である。すなわち、事業承継と後継者の選定、没後の同族会社の健全経営等、あらゆる面で総合的に考えた遺言が必要である。
b.障害のある子どもや未成年の子どもがいる場合
たとえば、身体に障害のある子どもに、他の子どもよりも多めに遺産を残しておきたいとか、相続人が未成年であるなど、親としては残された子どもの将来のことが非常に気になる場合は遺言をしておいたほうがよい。
3.遺産の分割協議がむずかしいと思われる場合
a.再婚して後妻と先妻の子供がいる場合
先妻の子どもと新しい妻との間は感情的に対立しがち。先妻の子どもにすれば、父が再婚しなければ全財産を相続できるはずであったのに、ということになる。一方、新しい妻の方は2分の1の相続分があるはずだと主張しがちである。夫としては、後妻も自分の妻であり、老後を共に過ごした人であるから、後妻の老後の生活の安定も図りたい。また、後妻には先妻の子どもたちと仲良くやっていってもらいたい。そのことを遺言の中で触れておく。
b.一部の相続人に生前贈与をしている場合
一部の相続人に生前贈与している場合、残りの財産の帰属について口頭で自分の考えを話していることが多い。しかし、口頭の遺言は認められていないのでかえって混乱が生じる。はっきりと遺言書で決めておくべきである。
c.遺産が不動産など分けにくい物である場合
現金や預金は分けるのが容易である。しかし、不動産の場合は分けにくく、相続人間で争いが生じる。それを避けるために、遺言書で分け方を決めておくとよい。
d.相続人の中に協調性のない人がいる場合
相続人の全員が協調性のある人の場合は、分割もスムーズにいくが、残念なことにそうではないケースもある。そのような場合に備え遺言書を書いておくと相続人は助かる。
e.夫婦間に子供がいない場合
夫婦に子供がいない場合、長年夫婦で協力して築き上げてきた財産なら、先立つ者としては全財産を配偶者に相続させたいと思うこともある。民法では、子や孫がいない場合には配偶者と親が、また親もいない場合には配偶者と兄弟姉妹が相続人と定められている。したがって、遺産の多くを配偶者に与えたいときは、どうしても遺言ではっきりさせておくべきである。
4.法定相続人がいない場合
遺産を引き継ぐ相続人がいない場合には、一定の手続きを経て国に財産が帰属する。生前世話になった人や親しい友人に財産を譲りたい、あるいは社会福祉団体などに寄附したいと考えているのであるならば、そのように遺言しておくことが必要である。
遺言書の種類とその特徴
1.自筆証書遺言
自筆証書遺言は、全文自分で書き(手書き)、日付、氏名押印が必要である。訂正する場合も細かな規定があるので、書き直したほうがよい。
これは、遺言書を1人で作成できるので簡単である。ただし、記載内容が不明確で、遺言者の意思がうまく表現されていなかったり、形式が遺言書と認められない例もあるから、弁護士に相談して書くことをお勧めする。
自筆証書遺言は、遺言者が死亡した場合、家庭裁判所で検認手続きをする必要がある。
2.公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人に作成してもらうもので、証人2人が必要である。
通常は公証人役場に出かけて作成するが、病気等で行けない場合は出張もしてもらえる。
この方式の場合、死後に遺言書の有効性が争いになることはほとんどない。
3.死亡危急者の場合の特別方式
死亡の危急に迫った者が遺言しようとする場合は、特別の方式がある。
これらをまとめると次の図表のようになる。
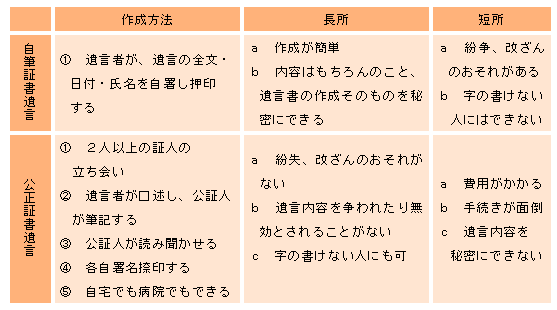
遺言書の例は、次のようになる。
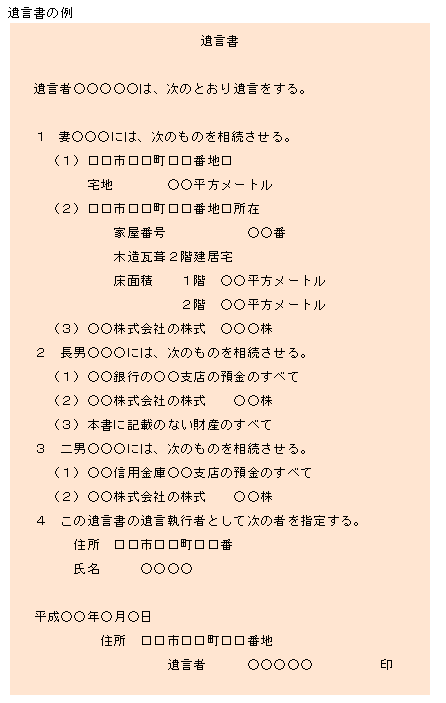
遺留分があること
被相続人の遺言により相続において財産を何ももらえなかったり、わずかしか財産をもらえない相続人が出るなど不公平が生じることがある。そこで、相続財産のうち一定割合額だけは相続人に保障しようとするのが遺留分の制度である。
1.遺留分権利者……配偶者、子、父母(兄弟姉妹には遺留分はない)
2.遺留分の割合……財産全体の2分の1(父母のみが相続人のときは3分の1)
たとえば、夫が死亡し、妻と長男、長女が相続人で、夫が長男に全財産2億円を与えると遺言していたケースでは、次のようになる。
・妻の遺留分=2億円×2分の1(遺留分率)×2分の1(法定相続分)=5,000万円
・長女の遺留分=2億円×2分の1(遺留分率)×4分の1(法定相続分)=2,500万円
妻は5,000万円、長女は2,500万円の遺留分を持ち、その分だけ財産を取り戻すことができる。この権利を遺留分減殺請求権という。
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が遺言分を侵害されたことを(遺言書の内容で)知ったときから、1年間行使しないときは時効により消滅する。
遺言書の保全
公正証書による遺言書は、公証役場に保管されているので、紛失のおそれはない。しかし、自筆証書や特別方式による遺言書は発見されにくい場所に隠しておくなどにより、遺言者の死後も発見されないままになってしまうことがある。
そこで、信頼のおける友人や税理士、弁護士に預けたり、銀行の貸金庫に預けたりして保管しておくのが望ましい。
遺言書が出てきたとき
公正証書による遺言書は、そのまま遺言書の内容を執行できる。
自筆証書や特別方式による遺言書は、公開されていないので、被相続人のものかどうかを確認(検認の請求)することが必要である。この検認(確認)は家庭裁判所で相続人立会のもとに開封して行なう。
著者
中山 昭男(相続コンサルタント)
2006年9月末現在の法令等に基づいています。
キーワード検索
タイトル検索および全文検索(タイトル+本文から検索)ができます。
検索対象範囲を選択して、キーワードを入力してください。



