ビジネスわかったランド (経営・社長)
経営計画の立て方・進め方
経営力分析の手順は
経営分析、経営活動分析、事業分析の3点から、次のように行なう。
経営力分析のフローチャート
自社の経営力分析の体系は、次の図表1のフローチャートに見るように、経営分析、経営活動分析、事業分析の3点から成る。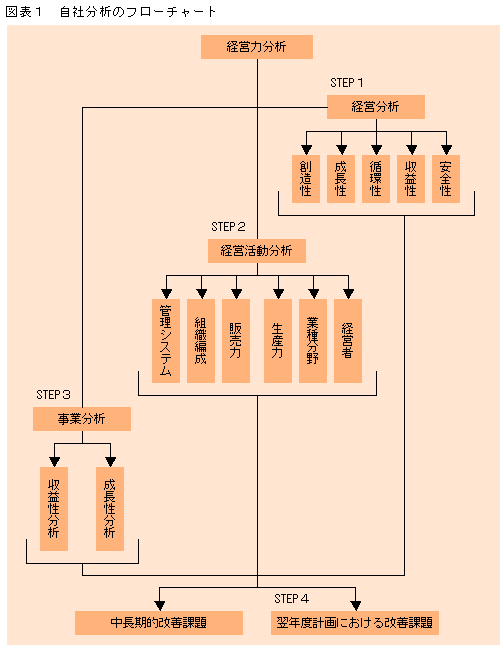
(STEP1)経営分析
経営分析は過去3年間の決算書をもとに、経営諸比率を計算し、安全性、収益性、循環性、成長性、創造性の5領域から総合的に点数評価するとともに、問題点と改善の課題を明らかにする。
(STEP2)経営活動分析
経営活動分析は、経営活動を経営者、業種分野、販売力、生産力、管理システム、組織編成の6領城から分析し、自社の伸ばすべき長所と改善課題を明らかにする。
(STEP3)事業分析
事業分析では、現在の事業の内容がいくつかの事業に細分化できる場合、あるいは単一事業でも市場や商品などで大きく区分できる場合、これらの事業あるいは市場、商品を成長性、収益性の面から分析するものである。
(STEP4)分析結果の総合と改善課題
最後に、これら3つの分析の結果を総合して自社の強みと弱みを整理し、中長期的な改善課題と翌年度における改善課題を整理する。
<< 自社の力を客観的に評価する >>
拡大と体質強化の成長バランス
「己を知り、敵を知れば百戦危うからず」のたとえのとおり、経営計画の策定においても、まず、自社の長所と改善点を明確に把握し、その長所を伸ばし、短所を改善するような戦略を計画に盛り込まなければならない。
企業の成長を見ていると、生産、販売などすべてにバランスをとりながら伸びているという例は割と少ない。まず、自社の長所を伸ばすことによって規模の拡大を目指し、後から短所を補いながらバランスを図っている企業が多いように思える。
たとえば、販売力の強い企業であれば、何よりも販売力を発揮させて市場を拡大することが成長につながる。
しかし、長所である市場の拡大だけを目指していては生産力や組織力に遅れをとる。積極経営でいき詰まった企業は、自社の得意とする分野にかたよった資源投入により経営バランスを欠いてしまった企業が多い。拡大した市場を維持するために生産力の強化や管理システムの改善を図り、バランスをとることが安定成長の秘訣である。
このためにも、企業の成長には、まず、正しく現状の経営力を把握することが必要であり、これが現状分析の第一の狙いである。
実態認識の共有化
現状分析の狙いの第二は、現状認識の共通化である。経営力の現状を、トップだけが認識するのでなく、トップ層と経営幹部層が現状認識を同じくしておかないと、同じ土俵で計画策定をすることができない。
同じ船の乗組員が、船が置かれている位置の認識がパラバラであったら、船を目的地に着けることは至難のわざである。しかし、現実には、経営者と幹部層の間に、また幹部層同士で、現状認識の差が大きい企業が多いのに驚く。そして、このことが社内対立や意思不疎通の原因となっているのである。
たとえば、営業幹部と製造幹部の見方は、どうしても自部門中心となってしまう。また、技術系の経営者は技術部門に寛大で、販売部門に厳しく当たったり(逆の場合もあるが)、管理部門出身の経営者は、販売力や生産力の強化以上に管理体制の強化を図る傾向がある。
そこで、みんなで、お互いに現状の問題点についての論議を通じて共通認識に立っておくことが改善計画の立案に欠かせないのである。
評価の計数化
立場の違いがあるから、参加者みんなの評価が完全に一致することはむずかしいとしても、少しでも認識を近づけるために評価はできるだけ計数で把握したい。経営分析数値などは実際の数値でつかめるので問題はないが、販売力、生産力、管理システムの状況など、定量化しにくいものも、計数的に把握することができるように工夫することが肝要である。
<< 経営分析による企業の現状分析 >>
経営分析の体系
経営分析による現状分析は、安全性、収益性、循環性、成長性、創造性の5つの領域から判断する。これらは、それぞれ人間の体にあてはめると、骨格、筋肉、血液循環、活力、頭脳に相当する。企業も人間と同じように五体のバランスを見て、自社の長所と改善すべき短所を明確に把握する必要がある。
(1) 安全性(骨格)……資本と資産のバランスから見た支払能力
(2) 収益性(筋肉)……投下資本や売上に対する獲得収益の割合
(3) 循環性(血液)……資金収支のバランスの善し悪し
(4) 成長性(活力)……時系列的に見た企業の伸び率
(5) 創造性(頭脳)……1人当りの売上、付加価値などの効率
企業の経営力をこれら5領域を各6項目で、計30項目にわたって評価する。評価基準は30数年の診断、指導の過程で得られた企業の質的分類に基づいた規範値を標準としているので、詳しくは 『創造経営経済学』(薄衣佐吉著、白桃書房)を参照してほしい。
ここでは、簡便法により、15の経営分析指標で100点満点で評価するようにしてある。その総合評価は次の図表2のとおりである。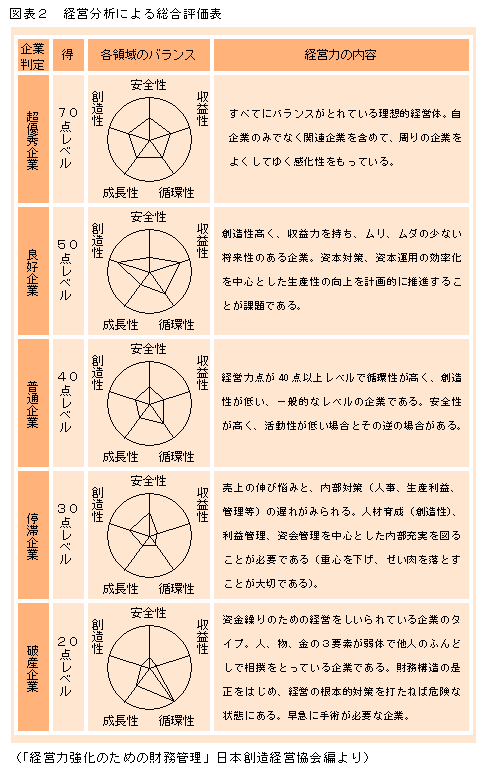
以下、5つの領域のそれぞれの経営分析指標について、評価と改善の着眼点について説明しよう。
安全性領域
安全性領城は、企業体質の健全度、安定力を測定する領域である。
企業活動は資本を調達し、それを資産へ運用することを通して利益を上げることを目的としているが、この運用資産に見合った資本が調達されていれば安全性は保たれる。
安全性は、株主資本比率、流動比率という資本面での安全性に加えて、人的な面での従業員定着率の3指標から測定する(図表3の計算式参照)。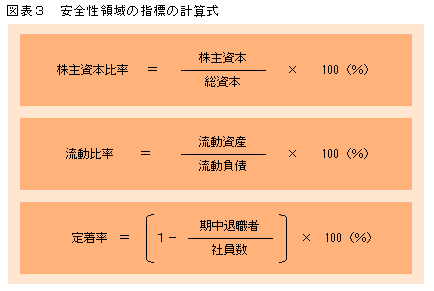
株主資本比率は、企業が投下している資本のうち、株主の投下資本および利益の蓄積部分の割合を示すもので、比率が高いほど安全性が高い。30%が分岐点で50%以上あれば優秀である。
流動比率は、短期的な企業の支払能力を示す指標である。1年以内に支払期限がくる負債と1年以内に回収される資産を対比したもので、この比率が高いほど支払能力があることを表わしている。130%以上はほしい。
従業員の定着率は人的な面での安全性を表わすものであり、定着率が高いほど技術の蓄積やロイヤリティーが高く、生産性の向上につながりやすい。反対に定着率が低い企業はいくら設備や資本を投下しても技術や信用の蓄積が進まず、生産性はあがらない。
収益性領域■企業経営の効率は、投下した資本に対してどれだけの利益を実現したかによってとらえられる。いたずらに売上高の増加のみに目を奪われ、原価、費用の管理をおろそかにしていては企業の成長発展は望めない
収益性は、売上高営業利益率、売上高経常利益率、経営資本に対する営業利益率の3指標で測定する(図表4の計算式参照)。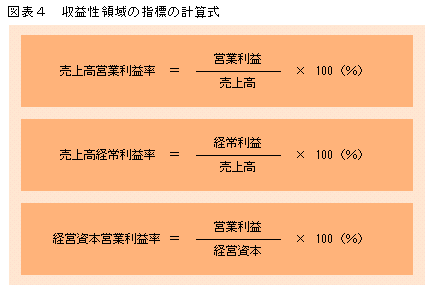
営業利益とは、企業本来の営業活動から生じた利益であり、これを売上高で除した売上高営業利益率は、営業活動の効率を判断する指標である。この比率が高いほど収益性がよい。業種によって違いはあるものの、7~8%はほしい。
経常利益は、営業利益に財務活勤による損益を加えた利益で、当期間の経営活動からもたらされた期間利益を表わしている。借入金が大きい企業は支払利息が多いために営業利益を下回るし、金融資産の運用による収益が大きい企業は営業利益を上回っている。
これも業種によって違いはあるが、一般的には5%はほしいところである。
経営資本とは、総資本から経営活動に直接寄与していない遊休不動産や投資資産などを控除した資産で、経営活動に直接関わっている資産をいう。
経営資本営業利益率は、経営活動に投下されている資本のリターンとして、営業活動から生じた営業利益の比率を見るものである。7~8%はほしい。
循環性領域
循環性は、経営の善し悪しを資本の循環のさせ方から判断する。企業が継続して活動を続けていくためには、その使用している資本の性質に応じた資産運用を心掛けるとともに、商品の仕入れから販売、回収までの期間と、仕入れから支払いまでの期間のバランスを図ることである。
循環性は、売上高支払利息比率、仕入債務対売上債権回転率比、経営資本回転率の3指標から測定する(図表5の計算式参照)。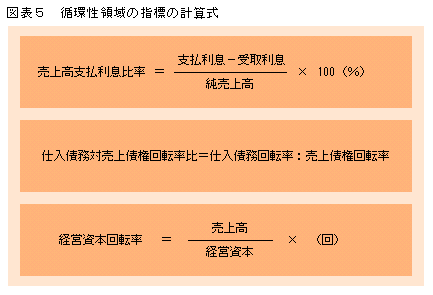
売上高に対する支払利息割引料の比率が高いということは、それだけ借入金や割引手形に依存していることを表わしており、資金循環の悪さを意味している。
また、この比率が高いほど収益性は低下する。一般に、この比率が3%を超えると企業の収益性回復は著しくむずかしくなる。
短期的な資金循環の善し悪しは、販売に伴う売上債権の回収の速さと、仕入債務の支払いの速さのバランスで決まる。すなわち、回収が支払いより常に先行している企業は運転資本が少なくとも資金は回っていくが、反対に支払いが回収に先行している企業はその支払いが先行する分だけ運転資本が必要となるからである。
このような考え方で支払いと回収の速度を比較して短期的な資金循環を測定しようとするのが、この仕入債務対売上債権回転率比である。
この比率の求め方は、次の図表6のように仕入債務と売上債権それぞれの回転率を計算し、仕入債務回転率を1とした場合の売上債権の回転率の比率を計算する。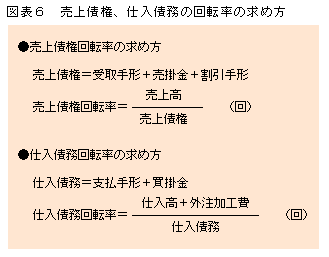
判断のポイントは、この比率が1であれば、回収と支払いの期間が一致していることを表わしている。1以上の場合には支払いに対して回収が速いのであるから、資金循環は良い。反対に1以下であると、支払いの期間より回収の期間が長いことを意味するから資金循環は望ましくない。
長期的な面での資金の循環性は経営資本回転率によって見ることができる。経営資本回転率は本来の営業活動に投下された資本が、どの程度、経営活動に活用されているかを判断する比率である。
経営資本の中身は現金預金、売上債権、棚卸資産、固定資産などに分けられるから、これらの活用度が高いほど経営資本回転率は高まる。経営資本回転率は、比較的使用資本が少ない中小企業では1.5回転ぐらいである。
成長性領域
企業が外部経済環境の変化に適応して活勤しているか否かを判断するのが成長性領域である。活動性ともいわれる。
成長とは、単に規模が膨らむことだけではなく、自己資本の増加など、実質的な経営体質強化につながるものでなければならないので、過去3年間の売上高増加率、付加価値増加率、自己資本成長率の3つの比率から測定する(図表7参照)。
売上高増加率は、毎期どのくらい売上高が伸びているかを分析するもので、少なくとも経済成長率以上の伸びが実現できていないと成長とはいえない。
グロスとしての売上高が伸びていても、それ以上に仕入や材料費、外注加工費など、外部への支払いが増えていては実質的な成長とはいいがたい。そこで、売上高から仕入原価など、外部購入原価を差し引いた付加価値の伸びで成長性の判断を補足する。
また、企業の成長は単に売上高や従業員数、総資本といった規模の拡大ではなく、質的な充実でなければならないが、この意味で、自己資本の増加こそ、実質的な成長と考えてよい。そこで、過去3年間の自己資本の伸び率を見る。
創造性領域
企業の創造性は、事業内容や商品力、あるいは生産システムの善し悪しなどを総合した力として評価されるが、これらの活動も結局のところ、企業の構成員一人ひとりの創造的な働きにかかっている。
創造性を、労働生産性や労働分配率、さらには企業構成員が創造性を発揮できるための条件の一つである人件費水準の2指標から測定する(図表8参照)。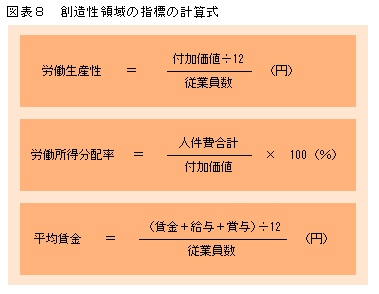
労働生産性は、企業が経営活動によって新しく生み出した付加価値を従業員数で割ったもので、付加価値の高い企業ほど社会的な貢献が大きく、また、収益率も高くなる。資本集約度によっても違うが、月間100万円以上はほしい。
労働分配率は、付加価値のうち、人件費に配分された割合を示すもので、適正人件費を前提として、分配率が低いほど一般に経営内容はよいと判断される。
企業成長のためには、労働分配率は45%程度に抑えたい。
平均賃金は、従業員の物心両面を満足させ、貢献意欲を引き出すための基礎的な判断材料となる。
平均賃金は、平均年齢や従業員構成など、また、業界の相場などによって異なるが、高いほどよいことはいうまでもない。問題は高い人件費を支払ってもなお、先の労働分配率を適正に抑えるような高い生産性を維持することが大切である。
<< 6つの領域から見る経営活動分析 >>
企業を見る4つの切り口
企業を理念レベル、戦略レベル、管理レベル、行動レベルの4面から見る見方がある。すなわち、企業が真に繁栄していくためには、次の図表9のように、理念、戦略、管理、行動のすべての面がしっかりしていなければならないというものである。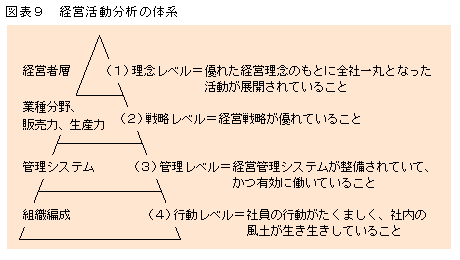
これらの4つのうち、どれかが欠けていれば良い経営はできないことは成長企業、倒産企業の実例に明らかである。
そこで、企業活動の分析にあたって、経営理念レベルから経営者の要因を、戦略レベルからは業種分野、販売力、生産力を、管理レベルからは管理システムを、そして行動レベルからこうした社員の行動を生み出す組織編成の6つを取り上げ、自社の経営活動分析項目とした(図表10参照)。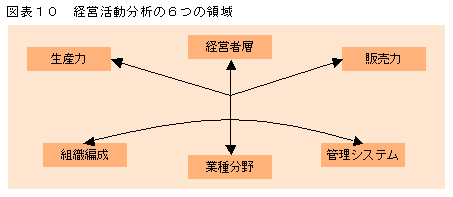
経営活動分析の体系
6つの分析項目の概要は次のとおり。
(1) 経営者層
経営者の行動に裏づけられた経営理念が全社に浸透していると共に、環境変化を先取りした経営戦略を構築し、経営革新のリーダーシップをとっているかという観点から6項目で分析する。
(2) 業種分野
自社の業種や扱い商品の成長性、および成長分野に進出するための開発体制の3項目で分析する。
(3) 販売力
ユーザーニーズをつかみ、商品企画に生かしながら、積極的、組織的に市場を開発すると共に、営業マンを生かすための販売管理が充実しているかどうかを5項目で分析する。
(4) 生産力
多品種少量生産に適応した生産システムを構築して、品質向上に努めると共に、新しい技術を積極的に取リ入れ、製品開発、技術開発を推進しているかどうかを5項目で分析する。
(5) 管理システム
経営戦略が経営計画に展開され、方針として管理されているか、また、そのための情報システムが整備されているかを3項目で分析する。
(6) 組織編成
組織が硬直化することなく、環境変化に適応できる柔軟性を備えていると共に、一人ひとりの意欲が喚起されて、組織が活性化しているかを3項目で診断する。
以上の6領域、その詳細評価項目である25項目は、図表11の経営活動分析事例を参考にされたい。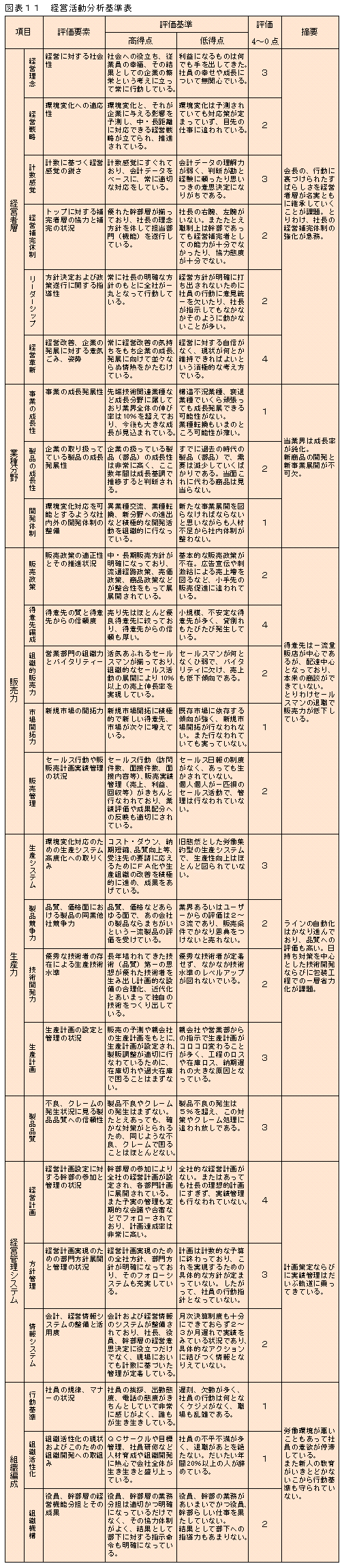
各4点満点の合計100点として評価し、自社の改善課題を明確にする。販売会社は生産力を除いて20項目、各5点で計算する。
経営活動分析基準表の使い方
図表11の経営活動分析基準表は、縦軸に分析項目、横軸に分析内容、分析基準が記述されている。分析要素は、分析項目ごとに評価すべき内容を掲げてあり、この評価内容に対する診断の基準として、高得点と低得点の内容が記述されている。
高得点と低得点の内容を読み、自社の現状を4点から0点までの範囲で評点欄に点数で記入する。
4点から0点は、おおよそ次を参考につける。
・4点=高得点の内容通りに実行されており、成果が上がっている
・3点=最近実行に取り組んでおり、成果が見えはじめている
・2点=現在、実行の準備をしている段階であり、これからに期待している
・1点=取り組まなければと思いながらも、日常業務などに追われてできていない
・0点=いままで、考えてもいなかったし、これから進めるつもりもない
チェックが終わったら、摘要欄に、6領城ごとに自社がこれから取り組まなければならない事項を整理して記入する。
<< 事業分析で伸ばす分野をつかむ >>
事業分析の体系
事業分析の着眼点は、その事業の成長性と投下資本に対する収益性の2つである。
よく知られているポートフォリオ分析は、事業を市場シェアと市場の伸び率のマトリックスから、「金の成る木」「花形商品」「問題児」「負け犬」の4つに分類するものである。しかし、中小企業の場合、事業別の市場シェアは著しく小さいことが多いので、ここでは、市場シェアのかわりに事業の収益性を用いて分析するように改良した。
市場成長性は、需要の伸び率と自社の伸び率から自社の成長度合を判断する。また、事業収益性は、投下資本に対する利益率と売上高利益率の2つによって判断する。
次の図表12は、これらをマトリックスに表わしたもので、横軸、事業の収益性は売上高利益率か資本利益率のいずれかを用いる。縦軸は市場の成長率と自社の事業ごとの売上高をとる。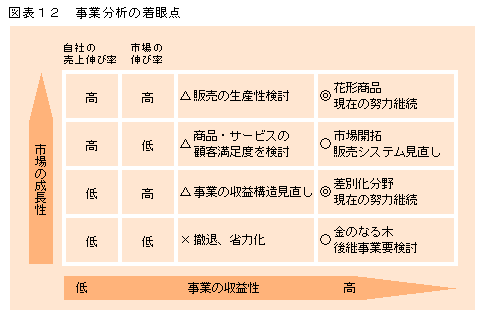
以上で8つの領域ができるが、これらの各領域に応じた戦略が求められることを示している。
事業の分類
事業をどのようにとらえるかは、企業によって違いがあってよい。
ミズノの例でいえば、大きく分ければスポーツ製造業、スポーツスペース業、スポーツサービス業の3つに分けられる。さらに製造業は、野球道具、ゴルフ用品などスポーツの種類ごとに分けることもできれば、スポーツ道具とスポーツウェアに分けることもできよう。
コンピュータ関連企業では、大きくハードとソフトに分類されて、ハードはさらにサーバ、オフコン、パソコン、といったようにそれぞれが細分化される。
まず、大きな分類でとらえて、さらに細分化してそれぞれの事業の成長性と収益性をとらえて伸ばすべき事業と撤退する事業と現状維持事業を明確にする。
また、単品商品を扱っている場合には、事業を分類せずに、全社を一つの事業とみなして成長性と利益性を求めてもよい。
市場成長性のとらえ方
市場の成長性は、産業界全体の伸び率と自社の伸び率を比較して判断する。
産業界の伸び率は、業界データなどから国内全体の出荷額や生産高をつかむが、場合によっては世界全体の出荷額や小規模企業の場合には地域の伸び率と比較してもよい。
自社の伸び率は、売上高あるいは生産高などでつかむ。
伸び率の比較時点のとらえかたによっては判断が異なる場合が出てくることもあるが、できれば過去数年にわたって伸び率の比較ができれば一層自社の位置が明確になろう。
事業収益性のとらえ方
事業収益は、投資利益率と売上高利益率の2面からとらえる。
(1) 投資利益率
その事業に投下している資本に対する事業利益の割合である。
まず、投下資本は、事業部制を採用している会社では事業部の投下資本をつかむことができるが、そうでない会社は投下資本をつかむことは必ずしも容易ではない。
そこで、直接把握できる投下資本は事業部ごとにつかみ、事業部に配賦されなかった共通の資本は事業部の直接資本あるいは売上高などで事業部に配賦して、その合計額を事業の投下資本とみなす(図表13参照)。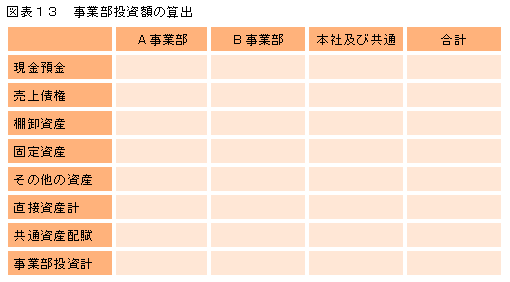
次いで利益であるが、事業部の貢献利益を用いる場合と、本社の配賦を控除した後の事業部純利益を用いる場合とがある。
貢献利益とは、事業部の粗利益から事業部固有の経費を控除した利益であり、これから本社の経費負担を控除したものが事業部純利益である(図表14参照)。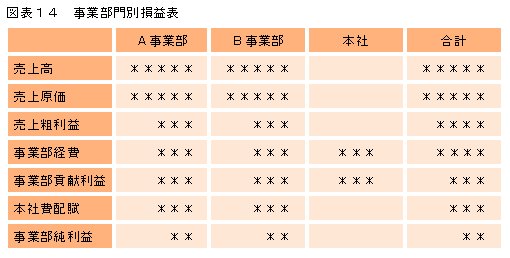
以上で投下資本と事業部利益が求められたが、ここで、事業部利益率は、図表15の算式で求められる。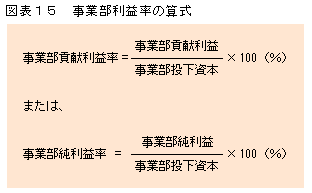
なお、事業部利益に貢献利益をとった場合と純利益をとった場合によって、求められる利益率が大きく異なるので注意が必要である。
(2) 売上高利益率
資本利益率が求められない場合には、代わりに売上高利益率を用いる。売上高利益率を計算する場合の利益率にも、貢献利益と事業部純利益率の両方を計算してみて判断する。
著者
天明 茂(公認会計士、宮城大学名誉教授)
2007年12月末現在の法令等に基づいています。
経営力分析のフローチャート
自社の経営力分析の体系は、次の図表1のフローチャートに見るように、経営分析、経営活動分析、事業分析の3点から成る。
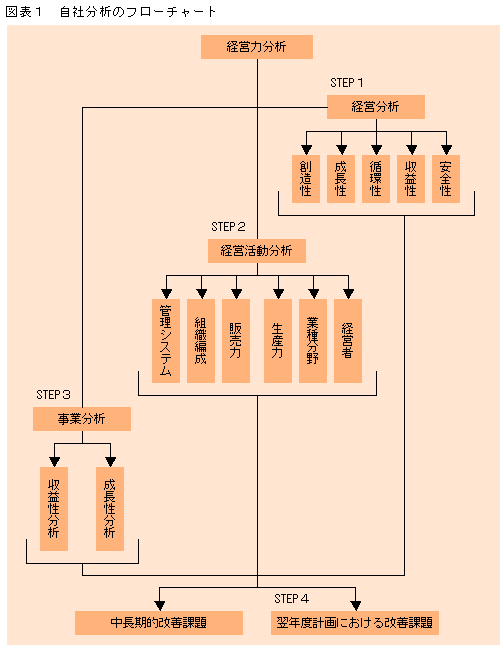
(STEP1)経営分析
経営分析は過去3年間の決算書をもとに、経営諸比率を計算し、安全性、収益性、循環性、成長性、創造性の5領域から総合的に点数評価するとともに、問題点と改善の課題を明らかにする。
(STEP2)経営活動分析
経営活動分析は、経営活動を経営者、業種分野、販売力、生産力、管理システム、組織編成の6領城から分析し、自社の伸ばすべき長所と改善課題を明らかにする。
(STEP3)事業分析
事業分析では、現在の事業の内容がいくつかの事業に細分化できる場合、あるいは単一事業でも市場や商品などで大きく区分できる場合、これらの事業あるいは市場、商品を成長性、収益性の面から分析するものである。
(STEP4)分析結果の総合と改善課題
最後に、これら3つの分析の結果を総合して自社の強みと弱みを整理し、中長期的な改善課題と翌年度における改善課題を整理する。
<< 自社の力を客観的に評価する >>
拡大と体質強化の成長バランス
「己を知り、敵を知れば百戦危うからず」のたとえのとおり、経営計画の策定においても、まず、自社の長所と改善点を明確に把握し、その長所を伸ばし、短所を改善するような戦略を計画に盛り込まなければならない。
企業の成長を見ていると、生産、販売などすべてにバランスをとりながら伸びているという例は割と少ない。まず、自社の長所を伸ばすことによって規模の拡大を目指し、後から短所を補いながらバランスを図っている企業が多いように思える。
たとえば、販売力の強い企業であれば、何よりも販売力を発揮させて市場を拡大することが成長につながる。
しかし、長所である市場の拡大だけを目指していては生産力や組織力に遅れをとる。積極経営でいき詰まった企業は、自社の得意とする分野にかたよった資源投入により経営バランスを欠いてしまった企業が多い。拡大した市場を維持するために生産力の強化や管理システムの改善を図り、バランスをとることが安定成長の秘訣である。
このためにも、企業の成長には、まず、正しく現状の経営力を把握することが必要であり、これが現状分析の第一の狙いである。
実態認識の共有化
現状分析の狙いの第二は、現状認識の共通化である。経営力の現状を、トップだけが認識するのでなく、トップ層と経営幹部層が現状認識を同じくしておかないと、同じ土俵で計画策定をすることができない。
同じ船の乗組員が、船が置かれている位置の認識がパラバラであったら、船を目的地に着けることは至難のわざである。しかし、現実には、経営者と幹部層の間に、また幹部層同士で、現状認識の差が大きい企業が多いのに驚く。そして、このことが社内対立や意思不疎通の原因となっているのである。
たとえば、営業幹部と製造幹部の見方は、どうしても自部門中心となってしまう。また、技術系の経営者は技術部門に寛大で、販売部門に厳しく当たったり(逆の場合もあるが)、管理部門出身の経営者は、販売力や生産力の強化以上に管理体制の強化を図る傾向がある。
そこで、みんなで、お互いに現状の問題点についての論議を通じて共通認識に立っておくことが改善計画の立案に欠かせないのである。
評価の計数化
立場の違いがあるから、参加者みんなの評価が完全に一致することはむずかしいとしても、少しでも認識を近づけるために評価はできるだけ計数で把握したい。経営分析数値などは実際の数値でつかめるので問題はないが、販売力、生産力、管理システムの状況など、定量化しにくいものも、計数的に把握することができるように工夫することが肝要である。
<< 経営分析による企業の現状分析 >>
経営分析の体系
経営分析による現状分析は、安全性、収益性、循環性、成長性、創造性の5つの領域から判断する。これらは、それぞれ人間の体にあてはめると、骨格、筋肉、血液循環、活力、頭脳に相当する。企業も人間と同じように五体のバランスを見て、自社の長所と改善すべき短所を明確に把握する必要がある。
(1) 安全性(骨格)……資本と資産のバランスから見た支払能力
(2) 収益性(筋肉)……投下資本や売上に対する獲得収益の割合
(3) 循環性(血液)……資金収支のバランスの善し悪し
(4) 成長性(活力)……時系列的に見た企業の伸び率
(5) 創造性(頭脳)……1人当りの売上、付加価値などの効率
企業の経営力をこれら5領域を各6項目で、計30項目にわたって評価する。評価基準は30数年の診断、指導の過程で得られた企業の質的分類に基づいた規範値を標準としているので、詳しくは 『創造経営経済学』(薄衣佐吉著、白桃書房)を参照してほしい。
ここでは、簡便法により、15の経営分析指標で100点満点で評価するようにしてある。その総合評価は次の図表2のとおりである。
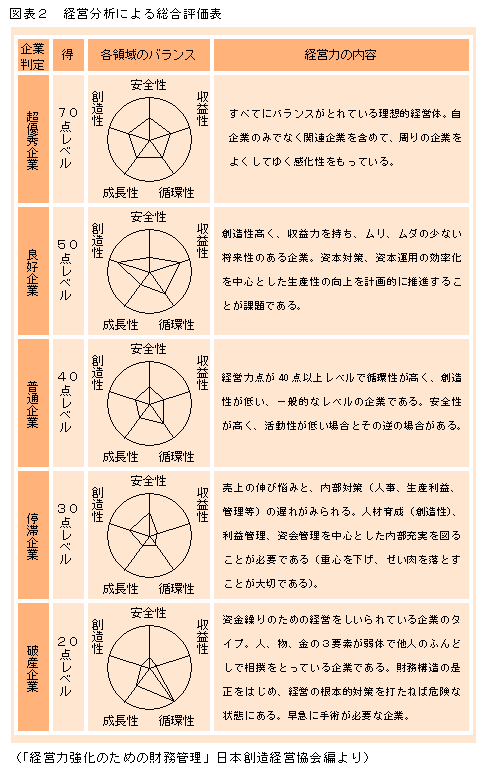
以下、5つの領域のそれぞれの経営分析指標について、評価と改善の着眼点について説明しよう。
安全性領域
安全性領城は、企業体質の健全度、安定力を測定する領域である。
企業活動は資本を調達し、それを資産へ運用することを通して利益を上げることを目的としているが、この運用資産に見合った資本が調達されていれば安全性は保たれる。
安全性は、株主資本比率、流動比率という資本面での安全性に加えて、人的な面での従業員定着率の3指標から測定する(図表3の計算式参照)。
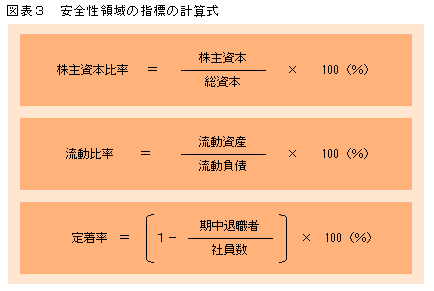
株主資本比率は、企業が投下している資本のうち、株主の投下資本および利益の蓄積部分の割合を示すもので、比率が高いほど安全性が高い。30%が分岐点で50%以上あれば優秀である。
流動比率は、短期的な企業の支払能力を示す指標である。1年以内に支払期限がくる負債と1年以内に回収される資産を対比したもので、この比率が高いほど支払能力があることを表わしている。130%以上はほしい。
従業員の定着率は人的な面での安全性を表わすものであり、定着率が高いほど技術の蓄積やロイヤリティーが高く、生産性の向上につながりやすい。反対に定着率が低い企業はいくら設備や資本を投下しても技術や信用の蓄積が進まず、生産性はあがらない。
収益性領域■企業経営の効率は、投下した資本に対してどれだけの利益を実現したかによってとらえられる。いたずらに売上高の増加のみに目を奪われ、原価、費用の管理をおろそかにしていては企業の成長発展は望めない
収益性は、売上高営業利益率、売上高経常利益率、経営資本に対する営業利益率の3指標で測定する(図表4の計算式参照)。
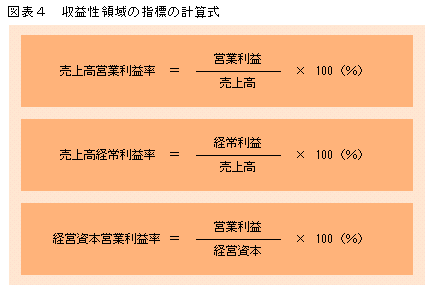
営業利益とは、企業本来の営業活動から生じた利益であり、これを売上高で除した売上高営業利益率は、営業活動の効率を判断する指標である。この比率が高いほど収益性がよい。業種によって違いはあるものの、7~8%はほしい。
経常利益は、営業利益に財務活勤による損益を加えた利益で、当期間の経営活動からもたらされた期間利益を表わしている。借入金が大きい企業は支払利息が多いために営業利益を下回るし、金融資産の運用による収益が大きい企業は営業利益を上回っている。
これも業種によって違いはあるが、一般的には5%はほしいところである。
経営資本とは、総資本から経営活動に直接寄与していない遊休不動産や投資資産などを控除した資産で、経営活動に直接関わっている資産をいう。
経営資本営業利益率は、経営活動に投下されている資本のリターンとして、営業活動から生じた営業利益の比率を見るものである。7~8%はほしい。
循環性領域
循環性は、経営の善し悪しを資本の循環のさせ方から判断する。企業が継続して活動を続けていくためには、その使用している資本の性質に応じた資産運用を心掛けるとともに、商品の仕入れから販売、回収までの期間と、仕入れから支払いまでの期間のバランスを図ることである。
循環性は、売上高支払利息比率、仕入債務対売上債権回転率比、経営資本回転率の3指標から測定する(図表5の計算式参照)。
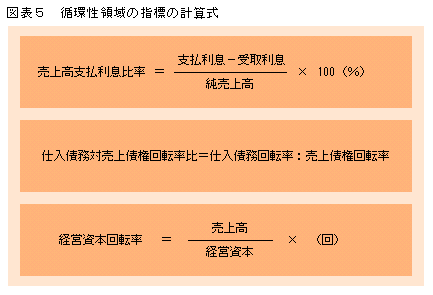
売上高に対する支払利息割引料の比率が高いということは、それだけ借入金や割引手形に依存していることを表わしており、資金循環の悪さを意味している。
また、この比率が高いほど収益性は低下する。一般に、この比率が3%を超えると企業の収益性回復は著しくむずかしくなる。
短期的な資金循環の善し悪しは、販売に伴う売上債権の回収の速さと、仕入債務の支払いの速さのバランスで決まる。すなわち、回収が支払いより常に先行している企業は運転資本が少なくとも資金は回っていくが、反対に支払いが回収に先行している企業はその支払いが先行する分だけ運転資本が必要となるからである。
このような考え方で支払いと回収の速度を比較して短期的な資金循環を測定しようとするのが、この仕入債務対売上債権回転率比である。
この比率の求め方は、次の図表6のように仕入債務と売上債権それぞれの回転率を計算し、仕入債務回転率を1とした場合の売上債権の回転率の比率を計算する。
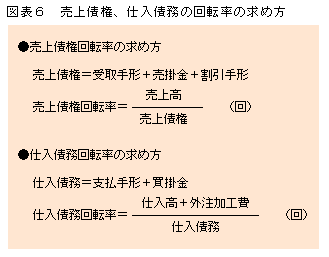
判断のポイントは、この比率が1であれば、回収と支払いの期間が一致していることを表わしている。1以上の場合には支払いに対して回収が速いのであるから、資金循環は良い。反対に1以下であると、支払いの期間より回収の期間が長いことを意味するから資金循環は望ましくない。
長期的な面での資金の循環性は経営資本回転率によって見ることができる。経営資本回転率は本来の営業活動に投下された資本が、どの程度、経営活動に活用されているかを判断する比率である。
経営資本の中身は現金預金、売上債権、棚卸資産、固定資産などに分けられるから、これらの活用度が高いほど経営資本回転率は高まる。経営資本回転率は、比較的使用資本が少ない中小企業では1.5回転ぐらいである。
成長性領域
企業が外部経済環境の変化に適応して活勤しているか否かを判断するのが成長性領域である。活動性ともいわれる。
成長とは、単に規模が膨らむことだけではなく、自己資本の増加など、実質的な経営体質強化につながるものでなければならないので、過去3年間の売上高増加率、付加価値増加率、自己資本成長率の3つの比率から測定する(図表7参照)。

売上高増加率は、毎期どのくらい売上高が伸びているかを分析するもので、少なくとも経済成長率以上の伸びが実現できていないと成長とはいえない。
グロスとしての売上高が伸びていても、それ以上に仕入や材料費、外注加工費など、外部への支払いが増えていては実質的な成長とはいいがたい。そこで、売上高から仕入原価など、外部購入原価を差し引いた付加価値の伸びで成長性の判断を補足する。
また、企業の成長は単に売上高や従業員数、総資本といった規模の拡大ではなく、質的な充実でなければならないが、この意味で、自己資本の増加こそ、実質的な成長と考えてよい。そこで、過去3年間の自己資本の伸び率を見る。
創造性領域
企業の創造性は、事業内容や商品力、あるいは生産システムの善し悪しなどを総合した力として評価されるが、これらの活動も結局のところ、企業の構成員一人ひとりの創造的な働きにかかっている。
創造性を、労働生産性や労働分配率、さらには企業構成員が創造性を発揮できるための条件の一つである人件費水準の2指標から測定する(図表8参照)。
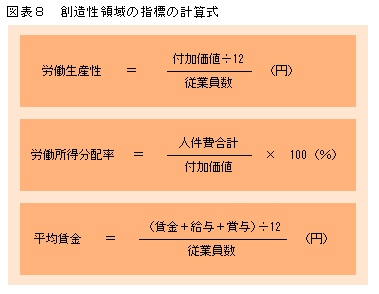
労働生産性は、企業が経営活動によって新しく生み出した付加価値を従業員数で割ったもので、付加価値の高い企業ほど社会的な貢献が大きく、また、収益率も高くなる。資本集約度によっても違うが、月間100万円以上はほしい。
労働分配率は、付加価値のうち、人件費に配分された割合を示すもので、適正人件費を前提として、分配率が低いほど一般に経営内容はよいと判断される。
企業成長のためには、労働分配率は45%程度に抑えたい。
平均賃金は、従業員の物心両面を満足させ、貢献意欲を引き出すための基礎的な判断材料となる。
平均賃金は、平均年齢や従業員構成など、また、業界の相場などによって異なるが、高いほどよいことはいうまでもない。問題は高い人件費を支払ってもなお、先の労働分配率を適正に抑えるような高い生産性を維持することが大切である。
<< 6つの領域から見る経営活動分析 >>
企業を見る4つの切り口
企業を理念レベル、戦略レベル、管理レベル、行動レベルの4面から見る見方がある。すなわち、企業が真に繁栄していくためには、次の図表9のように、理念、戦略、管理、行動のすべての面がしっかりしていなければならないというものである。
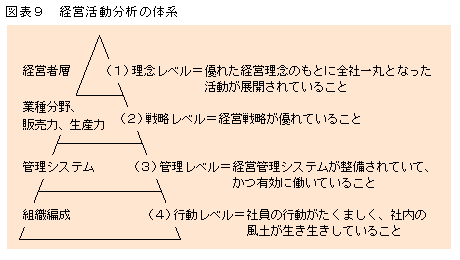
これらの4つのうち、どれかが欠けていれば良い経営はできないことは成長企業、倒産企業の実例に明らかである。
そこで、企業活動の分析にあたって、経営理念レベルから経営者の要因を、戦略レベルからは業種分野、販売力、生産力を、管理レベルからは管理システムを、そして行動レベルからこうした社員の行動を生み出す組織編成の6つを取り上げ、自社の経営活動分析項目とした(図表10参照)。
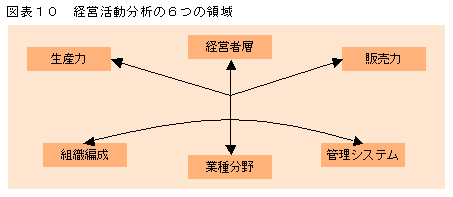
経営活動分析の体系
6つの分析項目の概要は次のとおり。
(1) 経営者層
経営者の行動に裏づけられた経営理念が全社に浸透していると共に、環境変化を先取りした経営戦略を構築し、経営革新のリーダーシップをとっているかという観点から6項目で分析する。
(2) 業種分野
自社の業種や扱い商品の成長性、および成長分野に進出するための開発体制の3項目で分析する。
(3) 販売力
ユーザーニーズをつかみ、商品企画に生かしながら、積極的、組織的に市場を開発すると共に、営業マンを生かすための販売管理が充実しているかどうかを5項目で分析する。
(4) 生産力
多品種少量生産に適応した生産システムを構築して、品質向上に努めると共に、新しい技術を積極的に取リ入れ、製品開発、技術開発を推進しているかどうかを5項目で分析する。
(5) 管理システム
経営戦略が経営計画に展開され、方針として管理されているか、また、そのための情報システムが整備されているかを3項目で分析する。
(6) 組織編成
組織が硬直化することなく、環境変化に適応できる柔軟性を備えていると共に、一人ひとりの意欲が喚起されて、組織が活性化しているかを3項目で診断する。
以上の6領域、その詳細評価項目である25項目は、図表11の経営活動分析事例を参考にされたい。
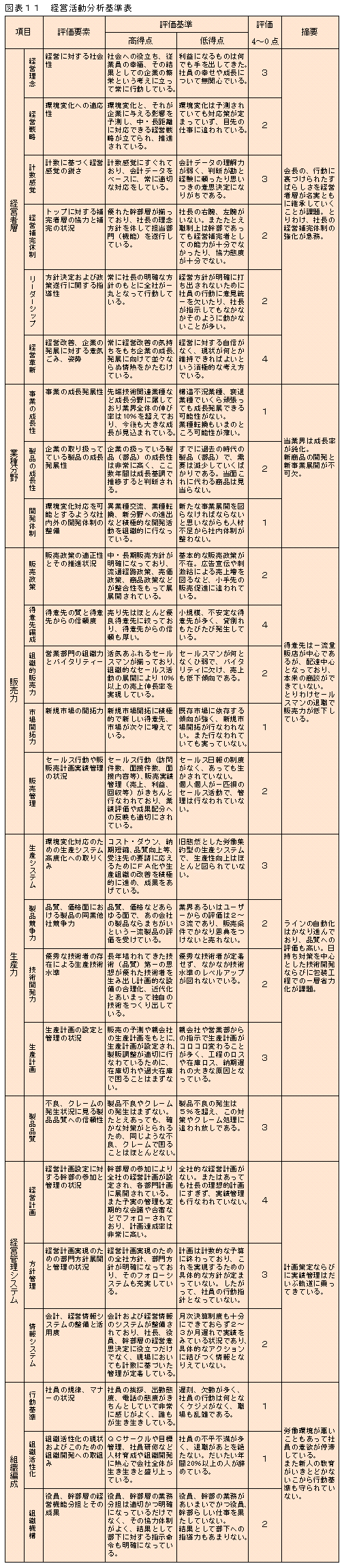
各4点満点の合計100点として評価し、自社の改善課題を明確にする。販売会社は生産力を除いて20項目、各5点で計算する。
経営活動分析基準表の使い方
図表11の経営活動分析基準表は、縦軸に分析項目、横軸に分析内容、分析基準が記述されている。分析要素は、分析項目ごとに評価すべき内容を掲げてあり、この評価内容に対する診断の基準として、高得点と低得点の内容が記述されている。
高得点と低得点の内容を読み、自社の現状を4点から0点までの範囲で評点欄に点数で記入する。
4点から0点は、おおよそ次を参考につける。
・4点=高得点の内容通りに実行されており、成果が上がっている
・3点=最近実行に取り組んでおり、成果が見えはじめている
・2点=現在、実行の準備をしている段階であり、これからに期待している
・1点=取り組まなければと思いながらも、日常業務などに追われてできていない
・0点=いままで、考えてもいなかったし、これから進めるつもりもない
チェックが終わったら、摘要欄に、6領城ごとに自社がこれから取り組まなければならない事項を整理して記入する。
<< 事業分析で伸ばす分野をつかむ >>
事業分析の体系
事業分析の着眼点は、その事業の成長性と投下資本に対する収益性の2つである。
よく知られているポートフォリオ分析は、事業を市場シェアと市場の伸び率のマトリックスから、「金の成る木」「花形商品」「問題児」「負け犬」の4つに分類するものである。しかし、中小企業の場合、事業別の市場シェアは著しく小さいことが多いので、ここでは、市場シェアのかわりに事業の収益性を用いて分析するように改良した。
市場成長性は、需要の伸び率と自社の伸び率から自社の成長度合を判断する。また、事業収益性は、投下資本に対する利益率と売上高利益率の2つによって判断する。
次の図表12は、これらをマトリックスに表わしたもので、横軸、事業の収益性は売上高利益率か資本利益率のいずれかを用いる。縦軸は市場の成長率と自社の事業ごとの売上高をとる。
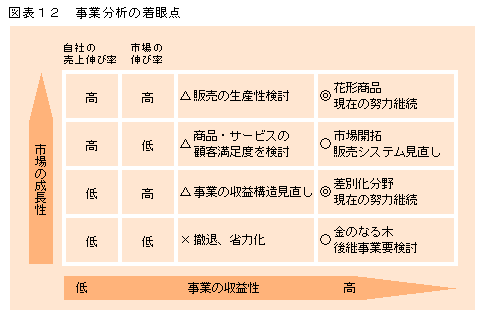
以上で8つの領域ができるが、これらの各領域に応じた戦略が求められることを示している。
事業の分類
事業をどのようにとらえるかは、企業によって違いがあってよい。
ミズノの例でいえば、大きく分ければスポーツ製造業、スポーツスペース業、スポーツサービス業の3つに分けられる。さらに製造業は、野球道具、ゴルフ用品などスポーツの種類ごとに分けることもできれば、スポーツ道具とスポーツウェアに分けることもできよう。
コンピュータ関連企業では、大きくハードとソフトに分類されて、ハードはさらにサーバ、オフコン、パソコン、といったようにそれぞれが細分化される。
まず、大きな分類でとらえて、さらに細分化してそれぞれの事業の成長性と収益性をとらえて伸ばすべき事業と撤退する事業と現状維持事業を明確にする。
また、単品商品を扱っている場合には、事業を分類せずに、全社を一つの事業とみなして成長性と利益性を求めてもよい。
市場成長性のとらえ方
市場の成長性は、産業界全体の伸び率と自社の伸び率を比較して判断する。
産業界の伸び率は、業界データなどから国内全体の出荷額や生産高をつかむが、場合によっては世界全体の出荷額や小規模企業の場合には地域の伸び率と比較してもよい。
自社の伸び率は、売上高あるいは生産高などでつかむ。
伸び率の比較時点のとらえかたによっては判断が異なる場合が出てくることもあるが、できれば過去数年にわたって伸び率の比較ができれば一層自社の位置が明確になろう。
事業収益性のとらえ方
事業収益は、投資利益率と売上高利益率の2面からとらえる。
(1) 投資利益率
その事業に投下している資本に対する事業利益の割合である。
まず、投下資本は、事業部制を採用している会社では事業部の投下資本をつかむことができるが、そうでない会社は投下資本をつかむことは必ずしも容易ではない。
そこで、直接把握できる投下資本は事業部ごとにつかみ、事業部に配賦されなかった共通の資本は事業部の直接資本あるいは売上高などで事業部に配賦して、その合計額を事業の投下資本とみなす(図表13参照)。
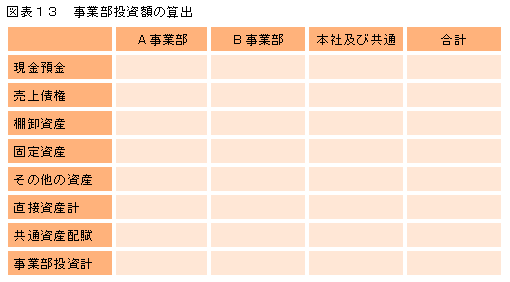
次いで利益であるが、事業部の貢献利益を用いる場合と、本社の配賦を控除した後の事業部純利益を用いる場合とがある。
貢献利益とは、事業部の粗利益から事業部固有の経費を控除した利益であり、これから本社の経費負担を控除したものが事業部純利益である(図表14参照)。
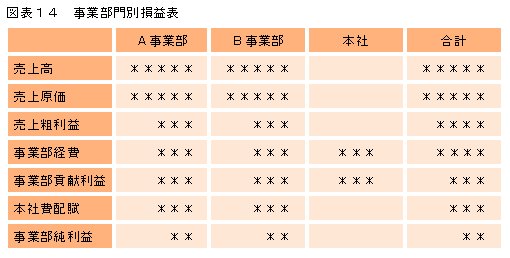
以上で投下資本と事業部利益が求められたが、ここで、事業部利益率は、図表15の算式で求められる。
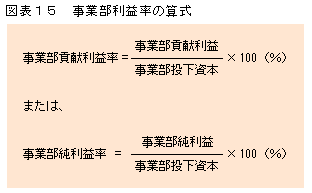
なお、事業部利益に貢献利益をとった場合と純利益をとった場合によって、求められる利益率が大きく異なるので注意が必要である。
(2) 売上高利益率
資本利益率が求められない場合には、代わりに売上高利益率を用いる。売上高利益率を計算する場合の利益率にも、貢献利益と事業部純利益率の両方を計算してみて判断する。
著者
天明 茂(公認会計士、宮城大学名誉教授)
2007年12月末現在の法令等に基づいています。
キーワード検索
タイトル検索および全文検索(タイトル+本文から検索)ができます。
検索対象範囲を選択して、キーワードを入力してください。



