ビジネスわかったランド (経営・社長)
経営計画の立て方・進め方
利益計画マスタープラン策定の手順は
経営重点方針に沿って、設備投資や人員計画、市場編成・商品構成計画などをもとに次のように利益計画の骨子(マスタープラン)を固める。
利益計画マスタープランのフローチャート
利益計画マスタープラン(骨子)は、経営重点方針に沿って、設備投資や人員計画、市場編成・商品構成計画などをもとに、図表1のフローチャートに従い、次のように行なう。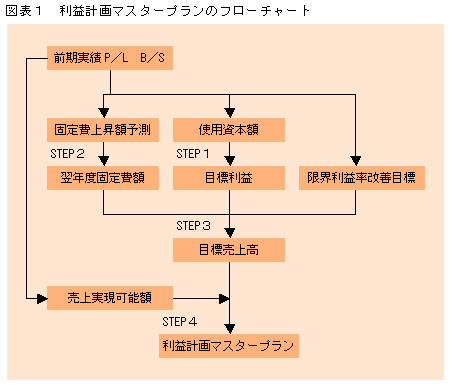
(STEP1)目標利益の設定
まず、自社の資本構成をもとに自社の規範利益を求め、前年度の実績利益を参考に翌年度の目標利益を設定する。
(STEP2)固定費の予測
次いで、今年度の固定費をもとに翌年度の固定費を予想する。
人件費は、定期昇給と増員の2面から、また、その他の製造固定費および販売管理固定費は、翌年度の増加率の概算を見込んで試算する。
(STEP3)目標売上高の計算
目標利益と固定費予測をベースにして、先の項(Q 市場編成・商品構成計画の着眼点は)で設定した商品構成別の限界利益率を考慮し、損益分岐点売上の計算式を活用して目標売上高を計算する。
(STEP4)利益計画シミュレーション
目標売上高の実現妥当性を検討し、目標利益、固定費額、限界利益率のシミュレーションにより翌年度の利益計画骨子を確定する。
<< 目標としての利益計画 >>
利益計画の骨子を固める
経営計画は、最終的に、共通言語としての会計数値で損益計算書としてまとめられるが、これはトップ層から示された基本方針と、これに基づいて下から積み上げられた計画とを調整して決められる。
利益計画マスタープランは、このトップ層の翌年度の基本利益計画として各部門計画を立案するときに、指針としての意味を持つものである。
マスタープランの段階では、詳細な予算の積上げは必要なく、概算予算の骨子でよい。
しかし、目標利益は、しっかりと押えなければならない。マスタープランの基礎は、目標利益だからである。
必要利益としての目標利益
利益は、結果ではない。獲得すべき目標である。通常、利益は、経営活動の結果として、収益-費用=利益
の形で示される。しかし、利益は、企業永続のための将来的費用ともいうべきもので、利益が計上できなければ企業の存続は望めない。
なぜなら、株主に満足してもらう配当は利益から払われるし、また、新規事業のための設備投資や商品開発などもすべて利益がその源泉となるからである。
このように考えると、利益は、企業成長のための将来的なコストとして、必ず実現しなければならないものである。
したがって、利益は、「結果」ではなくて、「目標」と考えるのが正しい。
いい替えれば、利益計画設定においては、
(1) 目標利益+必要費用=必要収益
あるいは、
(2) 実現可能収益-目標利益=許容費用
という考え方でなければならない。
(1)は、目標利益を獲得するために必要な収益を上げなければならないことを表わし、
(2)は、予想収益が限られている場合に、これから必要利益(目標利益)を差し引いて算出された許容範囲内にコストを抑えなければならないことを意味している。いずれも必要利益の確保が前提とされていることが大切な点である。
目標利益のとらえ方
企業は、いくらの利益を上げなければならないか。すなわち、目標とする利益をどのように求めるかについては、必ずしも定説があるわけではない。しかし、一般的には次のように考えられている。
(1) 投下資本にふさわしいと判断される利益
(2) 売上高に対する適正利益
(3) 借入金の返済に必要とされる利益
(4) 同業他社に負けない利益
(5) 自社の過去の平均以上の利益
企業の利益は、多いにこしたことはない。しかし、過大な利益を望むあまり、顧客から見放されたり、働く社員の利益を損なったりしては企業永続は望み得ない。
そこで、前記のような適正利益という考え方が出てくるのであるが、企業活動を資本の調達と運用による利益の獲得活動と考えれば、企業が投下している資本に対するコストあるいは必要収益という考えから目標利益を算出するのが論理的である。
そこで、ここでは、前記(1)の「投下資本にふさわしいと判断される利益」によって適正利益をつかみ、この実現可能性を検討したうえで目標利益を求めている。
貸借対照表のしくみ
それでは、投下資本に応じた目標利益の求め方を説明しよう。
貸借対照表は、「貸方」には企業が投下している資本の調達先が、また「借方」はその調達した資本の運用形態が示されている。
調達した資本の合計額=貸方資本合計が、運用された資産の内容としての資産=資産合計であるから、借方と貸方は常に等しく、ここからバランスシートの名が出ていることは周知のとおりである。
さて、「貸方」の調達資本は、
・他から調達してきた資本、すなわち他人資本=負債と、
・企業自身に帰属する資本である純資産
に分類される。
規範利益の考え方
ところで、資本構成から企業が必要とする利益を求める考え方は、この総資本を構成するそれぞれの資本に関わるコスト、あるいはその資本に求められる必要収益から必要利益を求めようとするものである。
この必要利益は、資本構成に応じた、あるべき利益であるから「規範利益」とよばれる。(図表2参照)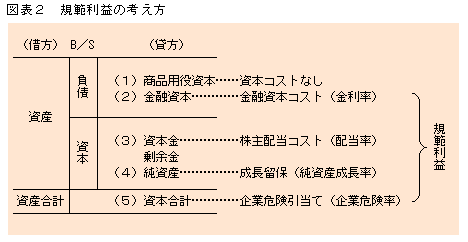
(1)商品用役資本は、商品仕入に伴う買掛金や支払手形であり、これらにはコストがかからないので除外してよい。
(2)の金融資本は、金融機関からの借入金や割引手形などで、借入れや割引に伴う金利が金融資本利子である。
(3)の資本金は、払込み資本金であり、発行株式数に対する配当金が配当留保である。
(4)の純資産のうち資本剰余金や利益剰余金は、配当金のような支払コスト負担はないが、資本金を含めた純資産を、企業の成長という観点から見れば、毎年増殖させなければならない。
経済全体が成長しているのに純資産の増殖がないとすれば、それは衰退を意味するから、少なくとも経済成長率くらいの成長は望みたい。そこで、これを規範利益に加える。
(5)の資本合計(総資本)は、資産の形で企業の経営活動に責献しているが、この資産は、いろいろな形で危険を抱えている。
たとえば、売掛金や受取手形については貸倒れの危険が、在庫については棚卸ロスや盗難、陳腐化の危険が、金融資産については為替の変動が、また、すべての資産について地震、火災といった危険に常にさらされている。これらの危険に対する引当てとして何がしかの利益を確保しておかなければならない。これが企業危険引当といわれるもので、通常,総資産の1%~3%が必要とされている。
以上、(2)から(5)までの合計額が総資本に関わる規範利益であり、これから目標利益を考えるのが合理的である。
ところが、これらは企業に留保しておかなければならない利益であるが、これらの利益には税金が発生する((2)の金融資本利子は税法上損金算入となるので税金引当の必要がない)。そこで、これらに関わる税金を加えてやらなければならない。
以上を整理したのが次の図表3である(『経営診断学入門』薄衣佐吉著、東洋経済新報社)。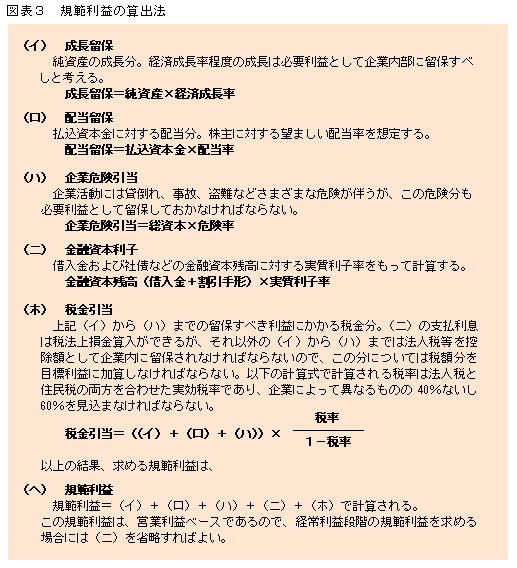
実際の目標利益の立て方
前掲の「規範利益の算出法」の式により規範利益の計算ができたら、これをもとに実際の目標利益を算出する。もちろん、適正利益がそのまま目標利益となることが望ましいことはいうまでもないが、実際には計算上求められた規範利益を計上するのは必ずしも容易ではない。
たとえば、毎年赤字の決算をしている企業にとっては、規範利益を計算してみても、絵に描いた餅でしかないかもしれない。逆に、高収益企業では規範利益が実績利益を上回ってしまう場合もあろう。
そこで、過去の営業利益を参考にし、また、現実の売上可能額を予測し、実現可能な限界利益率を参考に目標利益を算出する。
<< 固定費の計画 >>
固定費は付加価値を獲得するための犠牲コスト
マスタープランの段階では、利益計画の骨子であるから、固定費の計画は科目別に詳細に計画しなくとも、翌年度の伸び率を予測して概算固定費を計画することで足りる(図表4参照)。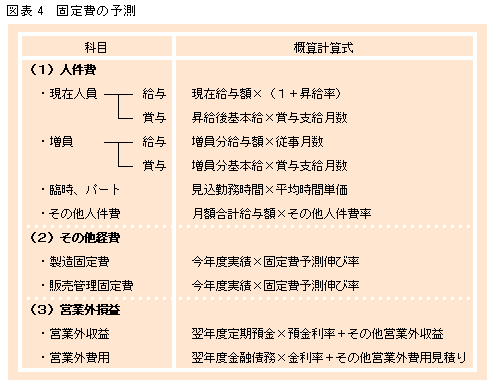
一般的に固定費は低く抑えることが理想とされるが、もともと固定費は付加価値を獲得するための犠牲コストであるから、支出固定費以上の付加価値が上げられれば固定費支出の価値があると考えられる。
もちろん、少なく抑えるにこしたことはないが、開発投資のように、現在の収益には貢献せずとも、将来の事業拡大や収益への貢献を狙いとした固定費を、投資という観点から支出することも政策的な配慮から必要である。
人件費の予測
人件費のうち、給与・賞与額は、社員については増員、昇給率、賞与支給月数を考慮して予測するほか、パートなど社員以外の給与額を加えて予測する。
給与、賞与以外の人件費については、福利厚生費、退職給与、同引当金など翌年度の予想伸び率から金額を予測する。
固定経費の予測
経費については、製造経費、販売管理費、そして営業外損益それぞれについて、翌年度の予測伸び率から翌年度固定費額を予測する。
主だった経費はそれぞれ伸び率を予想し、また、それ以外の経費については一括して伸び率を予測して固定費額を計画する。
また、翌年度固定費額には、研究開発投資や人材開発投資のうち、翌年度の期間費用となるものを計上しておく。
<< 限界利益率目標の設定 >>
変動損益計算
翌年度の限界利益率は、別項(Q 市場編成・商品構成計画の着眼点は)の商品構成あるいは市場編成計画で計画された限界利益率をそのまま用いる。
限界利益率は、限界利益を売上高で険して、次の図表5の式で求められる。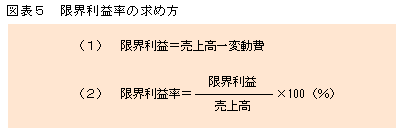
この限界利益率は、利益予測や利益計画にあたって威力を発揮するが、その前に、「変動損益計算」ということについて若干説明を加えておかなければならない。
普通の損益計算式は、図表6の左のように売上高から売上原価を控除して売上総利益を求める。売上総利益から販売費・管理費を差し引いて営業利益が求められ、これに営業外収益、費用を加減して経常利益が求められる。
これに対して変動損益計算は、図表6の右のように、売上から変動費を控除して限界利益を求め、これから固定費を差し引いて経常利益を求める。直接原価計算方式による損益計算の表わし方であり、利益管理の上からよく用いられる様式である。利益計画の設定においても、この「変動損益計算」の様式を使うと便利である。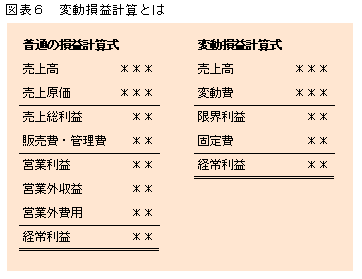
限界利益の威力
限界利益は、「売上高一変動費」として求められ、売上高に対する限界利益の率を限界利益率ということは、すでに述べたところである。
変動費とは、商品売上原価、製品の材料費や工場の燃料費など、生産や販売の増加に伴って発生する費用をいう。
限界利益率を使うと何が便利かというと、売上高が変化した場合の利益がすぐに求められることである。
たとえば、図表7の場合で、売上高が1,200万円に増加したときの利益は、どのように計算できるであろうか(ただし、販売費・管理費はすべて固定費とする)。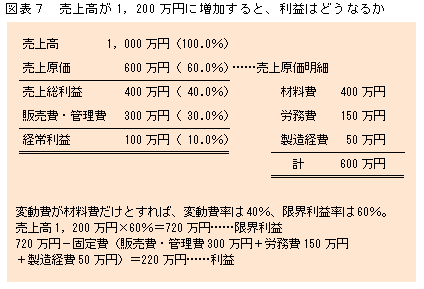
売上高1,200万円に売上総利益率40%を乗じて480万円の売上総利益を求めて、これから販売費・管理費300万円を控除して180万円の利益を計算するのはもちろん誤りである。なぜならば、売上原価には変動費である材料費と、固定費である労務費および製造経費が含まれているからである。
変動費を材料費だけであると仮定すれば、変動費率が40%ということから、限界利益率は60%と計算される。したがって、売上高1,200万円に限界利益率60%を乗じて720万円の限界利益を求めて、これから固定費500万円を控除すれば計上利益220万円を直ちに求めることができる。
このように、限界利益率と固定費額をつかむことができれば、売上高が変化した場合の計上利益額を予測することができるのである。
<< 損益分岐点を活用した必要売上高の計算 >>
必要売上高の計算
さて、いままでのステップで、翌年度における次の3つのデータが求められた。
(1) 目標利益
(2) 固定費予測額
(3) 限界利益率
ここまで予測できたら、あとは必要売上高を計算するだけである。必要売上高は、次の図表8の算式で計算できる。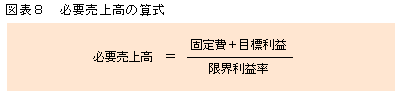
問題は、この売上高と、「Q 市場編成・商品構成計画の着眼点は」で計画した得意先別および商品別売上計画との整合性である。
利益計画シミュレーション
必要売上高が「Q 市場編成・商品構成計画の着眼点は」で設定した計画売上高を上回っている場合には、計画を修正する必要がある。
計画修正の着眼点は次の3つである。
(1) 限界利益率
(2) 固定費
(3) 目標利益額
必要売上高は先の図表8の算式で求められるが、こうして求められた必要売上高の実現可能性が薄いとなれば、必要売上高を引き下げなければならない。そのためには、算式の、分子を小さくするか分母を大きくするかのどちらかである。
前者は目標利益を引き下げるか、固定費を削減するかのいずれか。また、後者は限界利益率を高めることである。
再度「Q 市場編成・商品構成計画の着眼点は」に戻って、売上高および限界利益率を見直し、この3つを変化させたシミュレーションを繰り返して利益計画の骨子を固める必要がある。
参考までに、損益分岐点の説明を次の図表9に掲げておこう。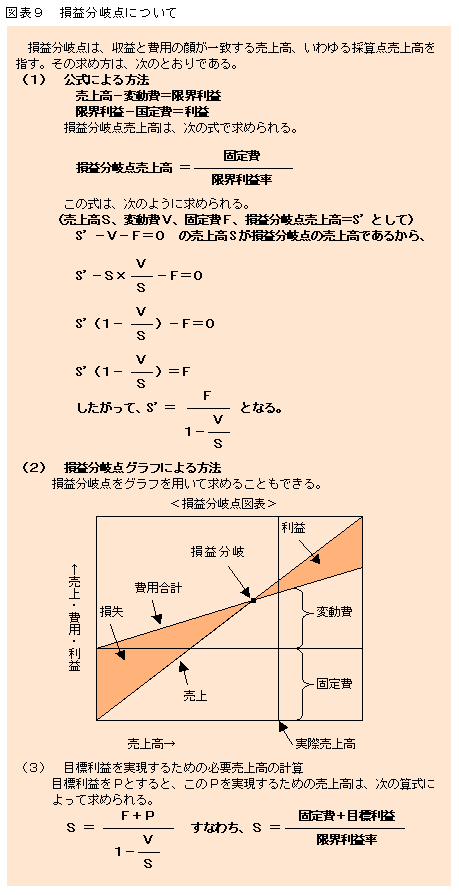
著者
天明 茂(公認会計士、宮城大学名誉教授)
2007年12月末現在の法令等に基づいています。
利益計画マスタープランのフローチャート
利益計画マスタープラン(骨子)は、経営重点方針に沿って、設備投資や人員計画、市場編成・商品構成計画などをもとに、図表1のフローチャートに従い、次のように行なう。
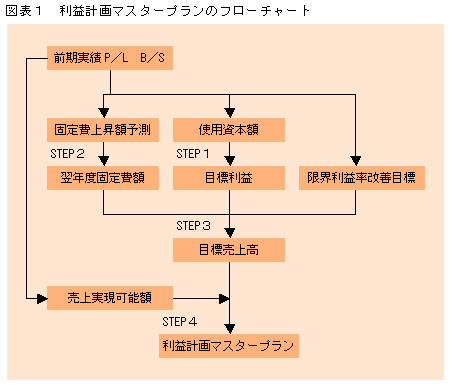
(STEP1)目標利益の設定
まず、自社の資本構成をもとに自社の規範利益を求め、前年度の実績利益を参考に翌年度の目標利益を設定する。
(STEP2)固定費の予測
次いで、今年度の固定費をもとに翌年度の固定費を予想する。
人件費は、定期昇給と増員の2面から、また、その他の製造固定費および販売管理固定費は、翌年度の増加率の概算を見込んで試算する。
(STEP3)目標売上高の計算
目標利益と固定費予測をベースにして、先の項(Q 市場編成・商品構成計画の着眼点は)で設定した商品構成別の限界利益率を考慮し、損益分岐点売上の計算式を活用して目標売上高を計算する。
(STEP4)利益計画シミュレーション
目標売上高の実現妥当性を検討し、目標利益、固定費額、限界利益率のシミュレーションにより翌年度の利益計画骨子を確定する。
<< 目標としての利益計画 >>
利益計画の骨子を固める
経営計画は、最終的に、共通言語としての会計数値で損益計算書としてまとめられるが、これはトップ層から示された基本方針と、これに基づいて下から積み上げられた計画とを調整して決められる。
利益計画マスタープランは、このトップ層の翌年度の基本利益計画として各部門計画を立案するときに、指針としての意味を持つものである。
マスタープランの段階では、詳細な予算の積上げは必要なく、概算予算の骨子でよい。
しかし、目標利益は、しっかりと押えなければならない。マスタープランの基礎は、目標利益だからである。
必要利益としての目標利益
利益は、結果ではない。獲得すべき目標である。通常、利益は、経営活動の結果として、収益-費用=利益
の形で示される。しかし、利益は、企業永続のための将来的費用ともいうべきもので、利益が計上できなければ企業の存続は望めない。
なぜなら、株主に満足してもらう配当は利益から払われるし、また、新規事業のための設備投資や商品開発などもすべて利益がその源泉となるからである。
このように考えると、利益は、企業成長のための将来的なコストとして、必ず実現しなければならないものである。
したがって、利益は、「結果」ではなくて、「目標」と考えるのが正しい。
いい替えれば、利益計画設定においては、
(1) 目標利益+必要費用=必要収益
あるいは、
(2) 実現可能収益-目標利益=許容費用
という考え方でなければならない。
(1)は、目標利益を獲得するために必要な収益を上げなければならないことを表わし、
(2)は、予想収益が限られている場合に、これから必要利益(目標利益)を差し引いて算出された許容範囲内にコストを抑えなければならないことを意味している。いずれも必要利益の確保が前提とされていることが大切な点である。
目標利益のとらえ方
企業は、いくらの利益を上げなければならないか。すなわち、目標とする利益をどのように求めるかについては、必ずしも定説があるわけではない。しかし、一般的には次のように考えられている。
(1) 投下資本にふさわしいと判断される利益
(2) 売上高に対する適正利益
(3) 借入金の返済に必要とされる利益
(4) 同業他社に負けない利益
(5) 自社の過去の平均以上の利益
企業の利益は、多いにこしたことはない。しかし、過大な利益を望むあまり、顧客から見放されたり、働く社員の利益を損なったりしては企業永続は望み得ない。
そこで、前記のような適正利益という考え方が出てくるのであるが、企業活動を資本の調達と運用による利益の獲得活動と考えれば、企業が投下している資本に対するコストあるいは必要収益という考えから目標利益を算出するのが論理的である。
そこで、ここでは、前記(1)の「投下資本にふさわしいと判断される利益」によって適正利益をつかみ、この実現可能性を検討したうえで目標利益を求めている。
貸借対照表のしくみ
それでは、投下資本に応じた目標利益の求め方を説明しよう。
貸借対照表は、「貸方」には企業が投下している資本の調達先が、また「借方」はその調達した資本の運用形態が示されている。
調達した資本の合計額=貸方資本合計が、運用された資産の内容としての資産=資産合計であるから、借方と貸方は常に等しく、ここからバランスシートの名が出ていることは周知のとおりである。
さて、「貸方」の調達資本は、
・他から調達してきた資本、すなわち他人資本=負債と、
・企業自身に帰属する資本である純資産
に分類される。
規範利益の考え方
ところで、資本構成から企業が必要とする利益を求める考え方は、この総資本を構成するそれぞれの資本に関わるコスト、あるいはその資本に求められる必要収益から必要利益を求めようとするものである。
この必要利益は、資本構成に応じた、あるべき利益であるから「規範利益」とよばれる。(図表2参照)
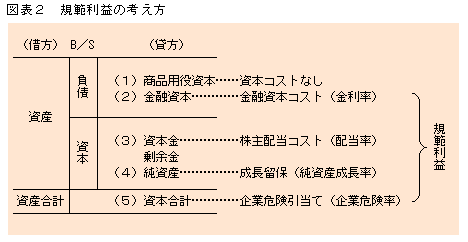
(1)商品用役資本は、商品仕入に伴う買掛金や支払手形であり、これらにはコストがかからないので除外してよい。
(2)の金融資本は、金融機関からの借入金や割引手形などで、借入れや割引に伴う金利が金融資本利子である。
(3)の資本金は、払込み資本金であり、発行株式数に対する配当金が配当留保である。
(4)の純資産のうち資本剰余金や利益剰余金は、配当金のような支払コスト負担はないが、資本金を含めた純資産を、企業の成長という観点から見れば、毎年増殖させなければならない。
経済全体が成長しているのに純資産の増殖がないとすれば、それは衰退を意味するから、少なくとも経済成長率くらいの成長は望みたい。そこで、これを規範利益に加える。
(5)の資本合計(総資本)は、資産の形で企業の経営活動に責献しているが、この資産は、いろいろな形で危険を抱えている。
たとえば、売掛金や受取手形については貸倒れの危険が、在庫については棚卸ロスや盗難、陳腐化の危険が、金融資産については為替の変動が、また、すべての資産について地震、火災といった危険に常にさらされている。これらの危険に対する引当てとして何がしかの利益を確保しておかなければならない。これが企業危険引当といわれるもので、通常,総資産の1%~3%が必要とされている。
以上、(2)から(5)までの合計額が総資本に関わる規範利益であり、これから目標利益を考えるのが合理的である。
ところが、これらは企業に留保しておかなければならない利益であるが、これらの利益には税金が発生する((2)の金融資本利子は税法上損金算入となるので税金引当の必要がない)。そこで、これらに関わる税金を加えてやらなければならない。
以上を整理したのが次の図表3である(『経営診断学入門』薄衣佐吉著、東洋経済新報社)。
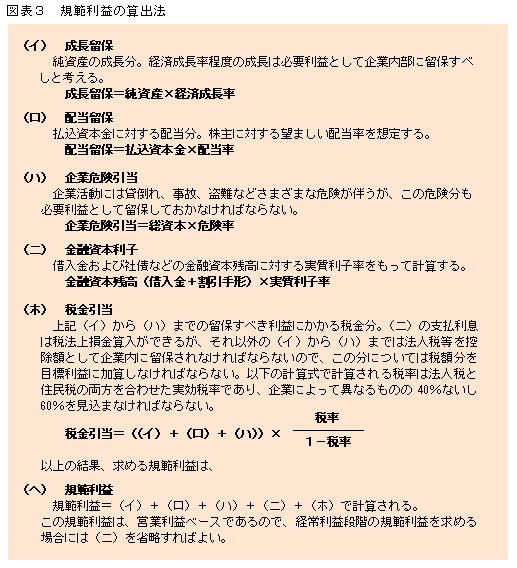
実際の目標利益の立て方
前掲の「規範利益の算出法」の式により規範利益の計算ができたら、これをもとに実際の目標利益を算出する。もちろん、適正利益がそのまま目標利益となることが望ましいことはいうまでもないが、実際には計算上求められた規範利益を計上するのは必ずしも容易ではない。
たとえば、毎年赤字の決算をしている企業にとっては、規範利益を計算してみても、絵に描いた餅でしかないかもしれない。逆に、高収益企業では規範利益が実績利益を上回ってしまう場合もあろう。
そこで、過去の営業利益を参考にし、また、現実の売上可能額を予測し、実現可能な限界利益率を参考に目標利益を算出する。
<< 固定費の計画 >>
固定費は付加価値を獲得するための犠牲コスト
マスタープランの段階では、利益計画の骨子であるから、固定費の計画は科目別に詳細に計画しなくとも、翌年度の伸び率を予測して概算固定費を計画することで足りる(図表4参照)。
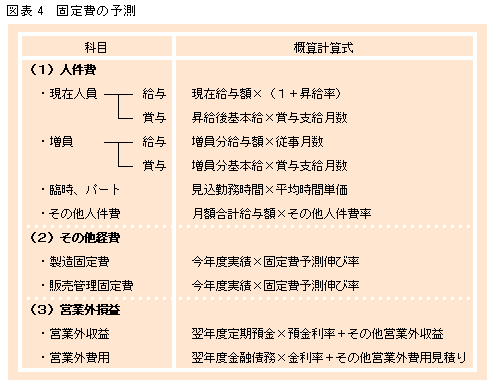
一般的に固定費は低く抑えることが理想とされるが、もともと固定費は付加価値を獲得するための犠牲コストであるから、支出固定費以上の付加価値が上げられれば固定費支出の価値があると考えられる。
もちろん、少なく抑えるにこしたことはないが、開発投資のように、現在の収益には貢献せずとも、将来の事業拡大や収益への貢献を狙いとした固定費を、投資という観点から支出することも政策的な配慮から必要である。
人件費の予測
人件費のうち、給与・賞与額は、社員については増員、昇給率、賞与支給月数を考慮して予測するほか、パートなど社員以外の給与額を加えて予測する。
給与、賞与以外の人件費については、福利厚生費、退職給与、同引当金など翌年度の予想伸び率から金額を予測する。
固定経費の予測
経費については、製造経費、販売管理費、そして営業外損益それぞれについて、翌年度の予測伸び率から翌年度固定費額を予測する。
主だった経費はそれぞれ伸び率を予想し、また、それ以外の経費については一括して伸び率を予測して固定費額を計画する。
また、翌年度固定費額には、研究開発投資や人材開発投資のうち、翌年度の期間費用となるものを計上しておく。
<< 限界利益率目標の設定 >>
変動損益計算
翌年度の限界利益率は、別項(Q 市場編成・商品構成計画の着眼点は)の商品構成あるいは市場編成計画で計画された限界利益率をそのまま用いる。
限界利益率は、限界利益を売上高で険して、次の図表5の式で求められる。
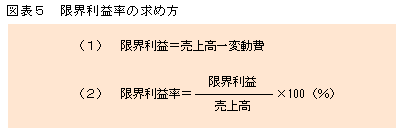
この限界利益率は、利益予測や利益計画にあたって威力を発揮するが、その前に、「変動損益計算」ということについて若干説明を加えておかなければならない。
普通の損益計算式は、図表6の左のように売上高から売上原価を控除して売上総利益を求める。売上総利益から販売費・管理費を差し引いて営業利益が求められ、これに営業外収益、費用を加減して経常利益が求められる。
これに対して変動損益計算は、図表6の右のように、売上から変動費を控除して限界利益を求め、これから固定費を差し引いて経常利益を求める。直接原価計算方式による損益計算の表わし方であり、利益管理の上からよく用いられる様式である。利益計画の設定においても、この「変動損益計算」の様式を使うと便利である。
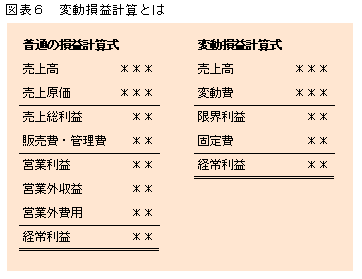
限界利益の威力
限界利益は、「売上高一変動費」として求められ、売上高に対する限界利益の率を限界利益率ということは、すでに述べたところである。
変動費とは、商品売上原価、製品の材料費や工場の燃料費など、生産や販売の増加に伴って発生する費用をいう。
限界利益率を使うと何が便利かというと、売上高が変化した場合の利益がすぐに求められることである。
たとえば、図表7の場合で、売上高が1,200万円に増加したときの利益は、どのように計算できるであろうか(ただし、販売費・管理費はすべて固定費とする)。
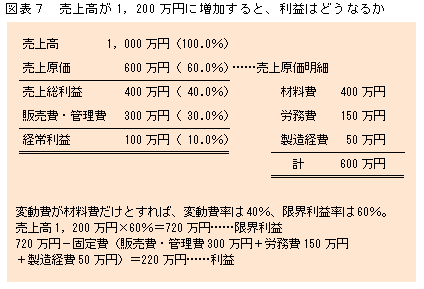
売上高1,200万円に売上総利益率40%を乗じて480万円の売上総利益を求めて、これから販売費・管理費300万円を控除して180万円の利益を計算するのはもちろん誤りである。なぜならば、売上原価には変動費である材料費と、固定費である労務費および製造経費が含まれているからである。
変動費を材料費だけであると仮定すれば、変動費率が40%ということから、限界利益率は60%と計算される。したがって、売上高1,200万円に限界利益率60%を乗じて720万円の限界利益を求めて、これから固定費500万円を控除すれば計上利益220万円を直ちに求めることができる。
このように、限界利益率と固定費額をつかむことができれば、売上高が変化した場合の計上利益額を予測することができるのである。
<< 損益分岐点を活用した必要売上高の計算 >>
必要売上高の計算
さて、いままでのステップで、翌年度における次の3つのデータが求められた。
(1) 目標利益
(2) 固定費予測額
(3) 限界利益率
ここまで予測できたら、あとは必要売上高を計算するだけである。必要売上高は、次の図表8の算式で計算できる。
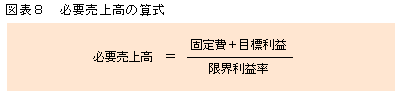
問題は、この売上高と、「Q 市場編成・商品構成計画の着眼点は」で計画した得意先別および商品別売上計画との整合性である。
利益計画シミュレーション
必要売上高が「Q 市場編成・商品構成計画の着眼点は」で設定した計画売上高を上回っている場合には、計画を修正する必要がある。
計画修正の着眼点は次の3つである。
(1) 限界利益率
(2) 固定費
(3) 目標利益額
必要売上高は先の図表8の算式で求められるが、こうして求められた必要売上高の実現可能性が薄いとなれば、必要売上高を引き下げなければならない。そのためには、算式の、分子を小さくするか分母を大きくするかのどちらかである。
前者は目標利益を引き下げるか、固定費を削減するかのいずれか。また、後者は限界利益率を高めることである。
再度「Q 市場編成・商品構成計画の着眼点は」に戻って、売上高および限界利益率を見直し、この3つを変化させたシミュレーションを繰り返して利益計画の骨子を固める必要がある。
参考までに、損益分岐点の説明を次の図表9に掲げておこう。
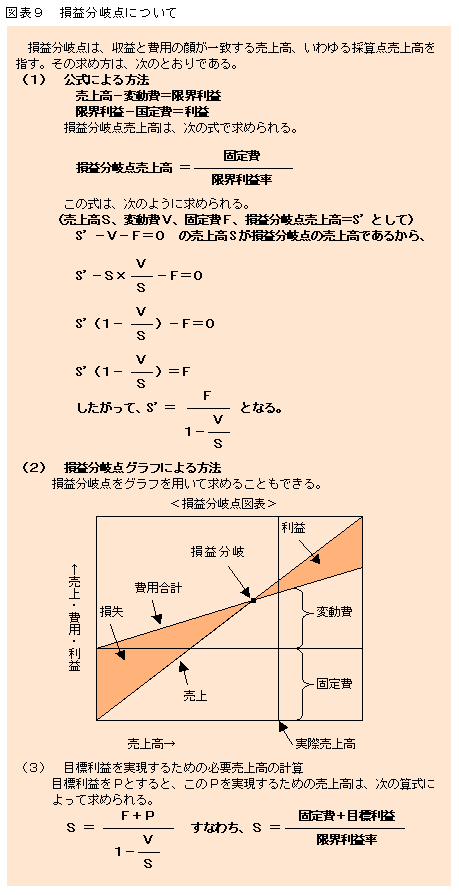
著者
天明 茂(公認会計士、宮城大学名誉教授)
2007年12月末現在の法令等に基づいています。
キーワード検索
タイトル検索および全文検索(タイトル+本文から検索)ができます。
検索対象範囲を選択して、キーワードを入力してください。



