ビジネスわかったランド (経理)
在庫管理
期末の棚卸資産の評価の仕方は
期末の棚卸資産の評価の方法としてはいくつかあるが、選択するに当たっては資産の種類や内容、事務能力などを勘案して決めることが肝要である。
<< 棚卸資産の期末評価 >>
棚卸評価=コストの配分
企業が収益を獲得するために要するコストの代表が棚卸資産である。商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品といった棚卸資産は、直接販売等されるとその取得価額はコスト(売上原価や製造原価)として売上高等の収益に見合わせて損益計算書に示される。
一方、期末時の棚卸資産は、次年度以降の収益に貢献すべきコストとして貸借対照表に計上される。すなわち決算では、一事業年度の棚卸資産の取得価額の合計額を、販売等された部分と残高部分とに分ける作業が生じる。これが、棚卸の評価(コストの配分)である。
損失処理が必要な場合も
貸借対照表に翌期以降の収益に貢献するコストとして取得価額を区分しても、期末時の時価が何らかの理由で取得価額以下に低下しているときは、コストとしての貢献部分を見直す必要が生ずる。つまり、もはやコスト貢献をしない部分は、ロスとして損失処理しなければならない。これも棚卸資産の評価として、重要な作業である。
この方法には、制度的な低価法によるものと、通常価格で販売できなくなったときに認められる評価損の計上とがあり、税務上はいずれも厳格な要件が求められる。
評価方法の種類と選択のポイント
コストの配分を行なう評価では、次表のような方法がある。
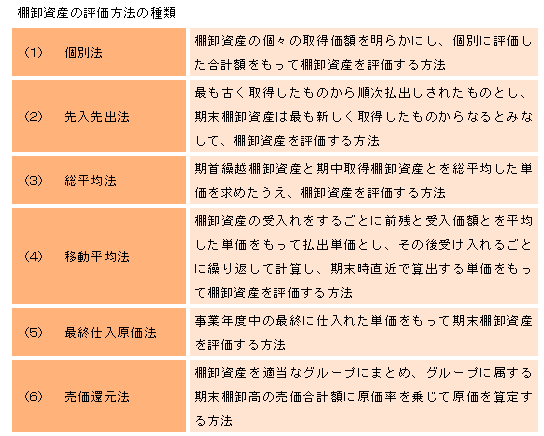
評価方法のどれを選ぶかは、棚卸資産の種類や内容のほか、棚卸資産のその企業での重要度や企業の事務能力なども勘案して決める。一般的に、それぞれ次のような特性があるとされている。
個別法は、個別の単価が高額でかつ個別管理に適した棚卸資産には適当であるが、量産品には不適当である。
先入先出法は、理論的な根拠をもつが、仕入原価の上昇や下落を考慮しないと損益に与える影響が大きく、総平均法はこの点を平均化したものであるといえる。
移動平均法は、総平均法以上に刻々推移する仕入単価を反映した評価が可能となるが、継続記録が行なわれることが前提である。
最終仕入原価法は、仕入価額の上昇時期には実際の取得価額を超えたり、逆の場合も生じ、簡便ではあるものの合理性に欠ける。
売価還元法は、取扱品種の多い百貨店等での採用が考えられるが、事務の簡便性などから製造業などでも便宜的に用いられることもある。
なお、以上は実際の取得価額をベースとした評価方法(原価法という)だが、期末時価のほうが低い場合は、それにより評価する低価法が制度的に認められている。より堅実な評価方法であり、選択が望ましい。
社内単価を活用するやり方も
棚卸資産、とりわけ商品や製品について実際の取得価額をベースとして算出した単価ではなく、いわば利益獲得を目的とした目標単価を設定し、営業担当者に対し目標単価以上での販売を求める方法がとられることがある。
また、実際の取得価額による単価は事後的にしか算出できないことから、あらかじめ期初に品目ごとの社内単価を設定し、受払いする企業も多い。
それぞれの単価のもつ意味は大きいが、激しく変化する企業環境の下で、一度設定された単価を弾力的に見直すタイミングもまた大切なポイントである。
税務上は、このような社内単価での期末棚卸資産評価は認められないため、期末時に原価差額の調整に準じた方法で、実際の取得価額に置き直す必要がある。
著者
渡辺 昌昭(公認会計士・税理士)
監修
税理士法人メディア・エス
2010年8月末現在の法令等に基づいています。
<< 棚卸資産の期末評価 >>
棚卸評価=コストの配分
企業が収益を獲得するために要するコストの代表が棚卸資産である。商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品といった棚卸資産は、直接販売等されるとその取得価額はコスト(売上原価や製造原価)として売上高等の収益に見合わせて損益計算書に示される。
一方、期末時の棚卸資産は、次年度以降の収益に貢献すべきコストとして貸借対照表に計上される。すなわち決算では、一事業年度の棚卸資産の取得価額の合計額を、販売等された部分と残高部分とに分ける作業が生じる。これが、棚卸の評価(コストの配分)である。
損失処理が必要な場合も
貸借対照表に翌期以降の収益に貢献するコストとして取得価額を区分しても、期末時の時価が何らかの理由で取得価額以下に低下しているときは、コストとしての貢献部分を見直す必要が生ずる。つまり、もはやコスト貢献をしない部分は、ロスとして損失処理しなければならない。これも棚卸資産の評価として、重要な作業である。
この方法には、制度的な低価法によるものと、通常価格で販売できなくなったときに認められる評価損の計上とがあり、税務上はいずれも厳格な要件が求められる。
評価方法の種類と選択のポイント
コストの配分を行なう評価では、次表のような方法がある。
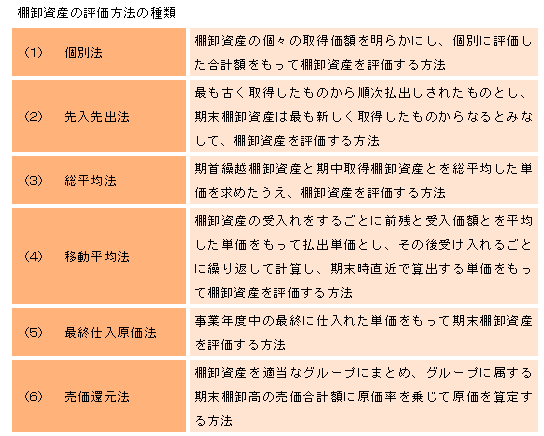
評価方法のどれを選ぶかは、棚卸資産の種類や内容のほか、棚卸資産のその企業での重要度や企業の事務能力なども勘案して決める。一般的に、それぞれ次のような特性があるとされている。
個別法は、個別の単価が高額でかつ個別管理に適した棚卸資産には適当であるが、量産品には不適当である。
先入先出法は、理論的な根拠をもつが、仕入原価の上昇や下落を考慮しないと損益に与える影響が大きく、総平均法はこの点を平均化したものであるといえる。
移動平均法は、総平均法以上に刻々推移する仕入単価を反映した評価が可能となるが、継続記録が行なわれることが前提である。
最終仕入原価法は、仕入価額の上昇時期には実際の取得価額を超えたり、逆の場合も生じ、簡便ではあるものの合理性に欠ける。
売価還元法は、取扱品種の多い百貨店等での採用が考えられるが、事務の簡便性などから製造業などでも便宜的に用いられることもある。
なお、以上は実際の取得価額をベースとした評価方法(原価法という)だが、期末時価のほうが低い場合は、それにより評価する低価法が制度的に認められている。より堅実な評価方法であり、選択が望ましい。
社内単価を活用するやり方も
棚卸資産、とりわけ商品や製品について実際の取得価額をベースとして算出した単価ではなく、いわば利益獲得を目的とした目標単価を設定し、営業担当者に対し目標単価以上での販売を求める方法がとられることがある。
また、実際の取得価額による単価は事後的にしか算出できないことから、あらかじめ期初に品目ごとの社内単価を設定し、受払いする企業も多い。
それぞれの単価のもつ意味は大きいが、激しく変化する企業環境の下で、一度設定された単価を弾力的に見直すタイミングもまた大切なポイントである。
税務上は、このような社内単価での期末棚卸資産評価は認められないため、期末時に原価差額の調整に準じた方法で、実際の取得価額に置き直す必要がある。
著者
渡辺 昌昭(公認会計士・税理士)
監修
税理士法人メディア・エス
2010年8月末現在の法令等に基づいています。
キーワード検索
タイトル検索および全文検索(タイトル+本文から検索)ができます。
検索対象範囲を選択して、キーワードを入力してください。



